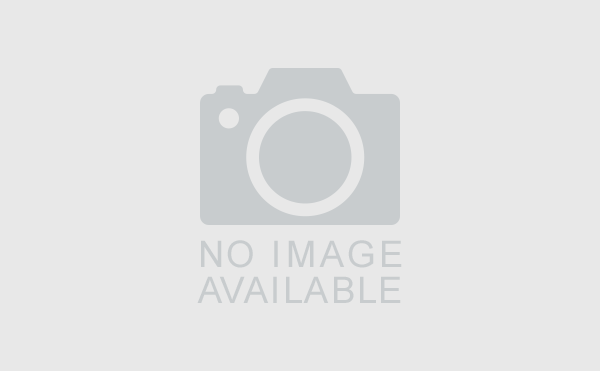請願第1号 LiD/APD(聞き取り困難症/聴覚情報処理障害)への公的支援及び理解啓発に関する請願に対する反対討論
◆1番(勝股修二) 勝股修二です。
ただいま議長からのお許しがありましたので、請願第1号 LiD/APD(聞き取り困難症/聴覚情報処理障害)への公的支援及び理解啓発に関する請願に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。
聴覚情報処理障害とは、聞こえているのに聞き取れない、聞き間違いが多いなど、音声を言葉として聞き取るのが困難な症状を指しています。通常の聴力検査では異常が発見されないこの症状は、耳から入った音の情報を脳で処理して理解する際に、何らかの障がいが生じる状態だと考えられています。
請願における願意の1つである発達障がい等による聞き取り困難症あるいは聴覚情報処理障害に対する教育上の配慮については、未来を担う子供たちを育てていくための取組として御提案をいただいたことに感謝を申し上げます。
しかし、LiDに対するワイヤレス補聴援助システムの購入に対する助成の制度化や貸出しの制度化について、議会として執行部に求めることは、以下の点により拙速であると考えます。
1点目に、助成を行うには、対象者を特定をしていく必要がありますが、聞き取り困難症や聴覚情報処理障害については明確な診断基準がなく、専門医による総合的な診断を要します。本症状について取り扱う専門医はまだまだ少なく、詳しい検査を求めて遠方まで足を運んだり、予約に数か月かかるなど、当事者の負担が非常に大きい状況です。その状況で、もし対象者を特定をしないとなると、制度としては大きな問題をはらむことになります。
2点目に、現在、様々な技術革新が行われており、状況は大きく変わりつつあります。アメリカ食品医薬品局(FDA)は、本年の現地時間9月12日に、AppleのAir Pods Pro2に搭載される補聴器機能を正式に承認したと発表しました。これはアメリカの話ですし、現在のところ、本商品は小児向けには推奨されませんので、すぐに適用できるわけではありませんが、医療機器である補聴器と、一般向けの商品の間の垣根がなくなりつつあるのは確かです。一般向けの商品が聞き取り困難症に対して有効であるとなった場合は、これらに対しても助成をする必要が出てきてしまいます。
これら2点から、対象者が明確でなく、対象品も明確でない状況であることを分かった上で助成を求めていくことは、議会として不誠実であると考えます。しかし、学習に対して何らかの影響を及ぼしている聞き取り困難症あるいは聴覚情報処理障害の疑いがある児童に対する教育現場における啓発と配慮については強く求めまして、本請願に対しての反対討論とさせていただきます。
本議案には勝股修二は反対させていただきましたが、賛成多数にて採択されました。
かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。