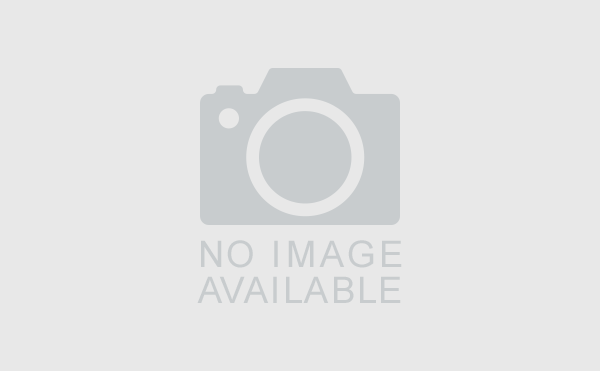介護分野における文書負担軽減等に向けた本市の取組について
◆1番(勝股修二) それでは、ただいま議長よりお許しをいただきましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。
愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
このような場で発言させていただく機会を尾張旭市民の皆様にいただけましたこと、本当に感謝申し上げます。1年生議員であり、行政経験もないものですから、至らないところは多々あるかと思います。市長をはじめ、執行部の皆様、また、並びに先輩議員の皆様にはぜひ御指導、御鞭撻をいただきますようよろしくお願いいたします。これから、尾張旭市民の皆様のために精いっぱいこの重責を務めさせていただきます。
私の本職は理学療法士といって、医療機関や介護関係の職場において、病気などにより身体が不自由になってしまった方のリハビリテーションのお手伝いをする職です。また、介護支援専門員、以下ケアマネといいますが、の資格も持っております。ケアマネは、要介護状態となってしまった方の生活や人生の質を向上させるよう、その方のケアサービスや社会資源などを手配していく、マネジメントをしていく職ではありますが、それらの職名をもって福祉、医療、介護の現場において長年働いてまいりました。そのような仕事をしつつも、近年のデジタル技術の発展に伴い、職場のICT化やセキュリティーについても取り組んでまいりましたので、初めての一般質問は私の現場経験を基に行わせていただきたいと思います。
大項目1に入ります。介護分野における文書負担軽減等に向けた本市の取組について。
一般に、福祉、医療、介護の世界では、人出不足が叫ばれています。きつい、汚い、給料が安いのいわゆる3Kの環境によって、働いている人が辞めていってしまう、介護の仕事に就こうという方が少ないといったことが長年続いているわけです。これといった解決策もないまま、我々の祖父や祖母、また両親、我々自身が要介護者となったときに、生活を助け、命を助け、人生の質を上げてくれる介護従事者の、見返りの少ない献身によって支えられているというのが現状です。かといって、市民の負担によって成り立っている社会保障費には限りがありますので、財源の裏づけもなく、報酬を上げるなどして無尽蔵に資金を投入すればよいというものではありません。限られた予算の中で、少しでも事態を改善するための手だてはないのでしょうか。
今回はその入り口として、事務負担の軽減について検討していきます。それこそお金や人手が足りないということで、それならば知恵をしっかりと尽くさなければいけないということで、お願いいたします。
介護や医療の現場で働いていると分かりますが、現場では、書類事務に関する負担が非常に大きい。利用者さんの基本情報や評価、計画、日々の記録、実施後の検証、再計画など、文書が非常に多岐にわたっております。それに加えて、事務所の指定に関わる申請や加算に関わる申請、契約書に重要事項説明書、また制度や訪問単価が変わるたびに求められる同意書など、事務負担は非常に膨大なものになっております。
皆様の保険料や税金が原資となっている介護保険ですので、それらの記録をおろそかにしていいというものではありませんが、介護報酬というのはあくまでも手を使った、手を動かしたものを評価するものですので、その事務負担が多いということは、それだけ実際の介護業務に関わる時間が減ってしまうと。つまり売上げが減ることによって、結果、介護従事者の給料が上がらないという悪循環に陥っているのです。それは、ひいては良質な介護を受けられる市民が減ってしまうということも意味しているので、文書負担の軽減というのは、市民の利益に直結していると私は考えます。
ケアマネにも同様のことが言えます。書類負担が多いために、多くの人をマネジメントすることができず、売上げが減り、ケアマネの収入も上がらない。負担の多さに比して収入が低い状況を目の当たりにしているケアマネ予備軍の方々が、ケアマネになりたがらない。結果、ケアマネ不足に陥って、ケアマネがいないために、介護サービスを受けたくても受けられない市民の方々が生じてしまうということも指摘をされております。
そこで、尾張旭市民がこれからも良質な介護サービスを受け続けられるようにするために、介護分野における文書負担軽減等に向けた本市の取組は現在どのようになっているのか、項目ごとに質問をさせていただきます。
⑴ 厚生労働省が示す文書負担軽減方針に対する本市の取組状況について
◆1番(勝股修二) 小項目(1)に入ります。厚生労働省が示す文書負担軽減方針に対する本市の取組状況について。
平成31年4月に、自民党厚生労働部会において、介護書類作成負担の軽減が提言されました。それを受けて、令和2年には厚生労働省より、「社会保障審議会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめを踏まえた対応についてが通知されております。
また、令和3年3月には、同じく厚生労働省より、「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」が通知されました。
そして、令和4年10月には、「介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について」とした事務連絡が厚生労働省より発出されております。これだけ、やっぱり厚生労働省としても文書の事務負担は多いといって考えておられて、それで各市町に対して何とか負担を減らしてくれないかということで、厚生労働省の方針も動いているわけです。
これらの厚生労働省からの文書を踏まえて、本市は具体的にどのような取組をなされているのか、お伺いします。答弁をお願いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
本市では、厚生労働省の示す負担軽減方針に沿う形で取組を進めており、介護サービス事業所指定申請書などへの押印廃止や、変更申請などの電子メールでの受付を行っております。
また、ホームページに提出書類の本市の様式を掲載しておりますが、厚生労働省や他の自治体の様式であっても、内容に不備がなければ受け付けることとしており、介護サービス事業所の事務負担の軽減を図っております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
厚労省の方針に沿う形で取組を進めている上に、本市以外の様式でも受け付けていただけるとのことです。しかし、各保険者、各市町、本当に微妙に記載内容が違う。ほとんど一緒なんですけれども、ちょこっと違うとか、市の処理欄が違うとか、なかなか事業所の立場としては使用をためらってしまうことと思います。この点、もう少し御検討をお願いしたいということで、小項目2のほうに移っていきます。
⑵ 介護分野の負担軽減に向けた独自ルールの精査、整理の状況について
ア 本市における独自ルールの精査、整理の状況について
◆1番(勝股修二) 介護事業所は、複数の市町、保険者にわたり事業を行っているところがほとんどであり、保険者によってルールや必要文書が違うことは、日々の業務や新人の研修などにおいて負担となっているということを介護の現場で働いている方からお聞きしますし、私自身、そのような感覚を持っておりました。
そのような御意見を踏まえてかと思いますが、本年3月30日に、「地域による独自ルール等に関する資料の公表について」と題して、厚生労働省老健局より事務連絡が発出されております。その中には、「各自治体におかれましては、資料を確認いただき、介護サービス事業所が負担と感じているルール等の内容を確認の上、独自ルールを精査いただき、真に必要なルール以外は、負担軽減の観点から整理を行うなどの対応をよろしくお願いいたします」との記載があります。これを踏まえて、本市はどのような独自ルールの精査、整理を行っているのか、お伺いいたします
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
本市では、事務上の独自のルールは特に設けておりませんが、保険者ごとに解釈を求められるものについては、介護保険事業者向けホームページに質疑応答として掲載し、周知を図っております。
また、厚生労働省から解釈の内容が明確に示された場合は、その解釈に合わせて適宜運用を変更しております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
本市では事務上の独自ルールを設けていないとのことですが、現場としては、尾張旭市は独自ルールでの運用をしているとの感覚が強いようで、いろいろな御意見も伺いますけれども、なかなか相互のコミュニケーションとか理解の問題もありますので、それこそ厚労省の文書において「介護サービス事業所が負担と感じているルール等の内容を確認の上」とありますように、介護サービス事業所のもっと意見を酌み上げていく体制というのをつくっていっていただきたいと思います。
イ 介護支援専門員との合意形成の充実について
◆1番(勝股修二) 次の質問に移ります。
イ、介護支援専門員との合意形成の充実についてということで、介護保険におけるサービスについてはケアマネのプランに基づいて行うという原則があり、ケアマネは各市町に示されたルールに基づいたプランを作成する必要があります。
先ほども御紹介した、令和3年3月の「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」という厚生労働省からの文書において、介護保険における各種ルールについては、「介護支援専門員の判断を十分に踏まえ、各市町村においては、その可否に係る判断にあたっては根拠を示し、双方が理解できる形で対応がなされるよう」特段の配慮が求められており、「双方の認識共有、合意形成の一層の充実に努められますよう」求められています。
そこで、本市と地域のケアマネジャーの双方が理解できる形の認識共有、合意形成の現状についてお伺いいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
本市では、年に一度、尾張旭市指定介護保険サービス事業者に対して、集団指導の場を設けております。その折に、変更届や加算の算定届などは、メールでも提出可能の旨を周知しております。また、各種様式を掲載しているホームページにおきましても、メールでの届出を推奨しているところです。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
集団指導の場で伝達をしていただいているということですけれども、そのような場ですと一方通行なコミュニケーションになることが多く、双方が理解できる双方向のコミュニケーションが不足しているとも感じます。
私が働いていた他市の事例にもなりますが、それこそケアマネの連絡会、またセラピスト、療法士の連絡会に、本当に頻繁に課長級以下、複数の行政職員が同席をしていただき、地域の実情に応じた地域包括ケアを官民協力してつくり上げていくと、そのような取組にも私自身、携わってまいりました。尾張旭市でもそのような取組しておられると思いますが、今後も引き続き官民協力していくということをお願いしたいと思います。
また、集団指導の場とかホームページでは、地域全体の合意形成にはなかなか至らないと思いますので、官民双方が理解をできる、納得できる形の認識共有や合意形成の場を設けていただきますように要望いたします。
⑶ 介護分野の厚生労働省により提示されている標準書式以外の電子文書について
ア 介護分野における入力用電子文書の見直しについて
◆1番(勝股修二) それでは、小項目(3)に移ります。
小項目(3)、介護分野の厚生労働省により提示されている標準書式以外の電子文書について。
ア、介護分野における入力用電子文書の見直しについて。
介護の現場においては、同じ書式を繰り返し継続的に使用して文書を作成することが多いことから、コンピューターなどの電子機器の普及により、かなり負担が軽減されてきました。しかし、行政から提示されるワードファイルやエクセルファイルなどについては、作成者個々の知識や技術に依拠した形式になっていることが多く、非常に入力しにくいものが多い印象です。エクセルファイルを方眼紙のように使うのは、データの再利用の観点からも避けるべき悪習であると考えています。
これらの文書について、現場の意見を踏まえるなどして、入力しやすい文書の整備について御検討いただけるか、お伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
介護分野の厚生労働省により示されている標準様式以外の文書につきましては、介護保険制度開始時に各様式を定め、以来、必要に応じて改正してきており、その入力用電子文書につきましては、利用者をはじめケアマネジャーや事業者の負担軽減に資するため、ホームページに掲載しているところです。
現時点において、入力用電子文書の内容やその操作性などについて改善の要望が多く寄せられている状況ではありませんが、不備や不具合がないか定期的に検証し、必要に応じて見直しをしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 定期的な検証、見直しをいただけるとの前向きな答弁、本当にありがとうございます。
改善の要望は多くは寄せられていないということなんですけれども、正直な話、介護分野の現場の皆さんもコンピューターに詳しい方というのはほとんどいらっしゃらないものですから、入力のしにくい電子文書をそのまま受け入れているというところもあると思います。
この点、行政が音頭を取って、現場の業務効率を上げていくとか、また現場の方がこうすれば効率的にできるのかということで、気づきを得られるように取り組んでいただくように、何とぞお願いいたします。
それでは、次の質問に移ります。
イ 近隣市町との共通化について
◆1番(勝股修二) イ、近隣市町との共通化について。
小項目(2)においても述べましたが、介護事業者は複数の市町にわたってサービスを提供しており、利用者の住所地に合わせて書類を作成する必要があります。全国共通の介護保険制度なのですが、必要とする文書は各市町により微妙に異なっており、これも文書負担の一因ともなっています。
そこで、まずは近隣市町だけでも共通化して、少しでも負担を軽減していただきたいということで、近隣市町と協議して文書を共通化していただくことはできませんでしょうか、お尋ねします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
介護分野の厚生労働省により示されている標準様式以外の文書については、各市町村でそれぞれ定めることとなっており、その様式は特に統一されておりません。
近隣市に確認したところ、それぞれの市が、利用者などが分かりやすいよう、かつ担当者が審査しやすいよう工夫しているとのことでしたが、今後、制度改正などによって大きく様式などを見直す必要が生じた折に、共通の様式を考える、そのことについて近隣市と協議、検討したい、そのように考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) こちらも前向きな御答弁と、もう既にほかの市町に確認をしていただいたということで、本当にありがとうございます。
これまでは、それぞれの市町、また単独の市町で、利用者等が分かりやすいよう、担当者が審査しやすいよう工夫されているとのことですが、やっぱり三人寄れば文殊の知恵とありますように、より多くの知見を結集すれば、より分かりやすく、より審査しやすくできると思います。
また、電子文書を作成する手間にしても、2つの市町が集まれば負担は半分に、また3つの市町が集まれば負担は3分の1ということですが、協議をする必要がある以上、算数のようにはいかないかもしれませんけれども、単独で行うより負担が減るんじゃないかなとは思います。行政事務の負担が減る上に介護事業者の負担も減るという、よいことばかりかと思いますので、近隣市町との協議、検討は、大きな改正を待つことなく行っていただきたいことを要望として申し上げます。
現在の超少子高齢化というのはまさに国難であり、このままでは我々の人生のラストステージが不幸な状況になってしまうかもしれない。将来世代にもその負担を負わせてしまうかもしれない。それを避けるためにも、将来世代のための少子化対策と、高齢化問題のための介護保険制度、地域包括ケアシステムの構築が不可決となっています。
介護保険や地域包括ケアシステムについては常に制度が見直されており、官民ともに負担の多い状況です。制度をつくっている厚生労働省すら、その発出する文書、先ほど紹介した文書の中にあるんですが、もう本当に誤字脱字がそこらじゅうにあるという状況で、本当に厚生労働省の負担も大きいと。
また、非常にタイムリーだったんですが、本市介護保険課においても送付した文書に間違いがあったということで、非常に大変な思いをしておられるということは分かりますが、それでもしっかり見直しをしていただいて、間違いのないように進めていっていただきたいと思います。
地域の実情に応じた独自施策を行っていくことも大事なんですけれども、独自でなくてもよい部分を見極めて、効率化できるところは効率化していく、労力を省けるところは省いて、官民双方の負担を減らしていく視点を持って対応していただきたいと思います。
現場の声を聞いていると、どうも行政機関との間に壁を感じているようで、一方的に指導されているというふうに感じている方も見えます。介護分野の皆様は、制度に沿った指導をされながらも、行政は自分たちの負担を減らそうとしてくれているんだと、現場にいる自分たちのことを気にかけてくれているんだということで思っていただくように、本当に現場の意見を聞いてくれていると実感することができれば、介護の現場の皆様のモチベーションも上がりますので、官民力を合わせてよりよい制度をつくり上げていくことができるのではないでしょうか。よりよい介護保険制度、地域包括ケアシステムが構築されていくことを祈りつつ、大項目2に移ります。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。