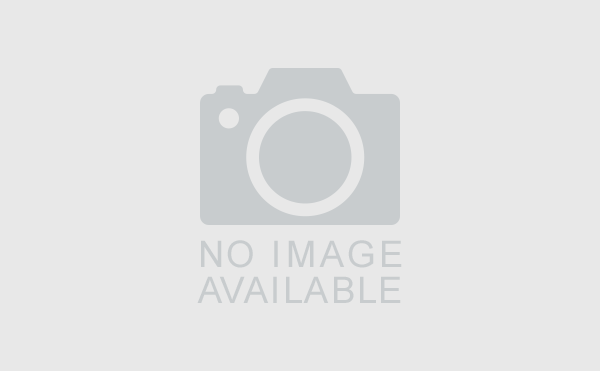令和5年9月定例会質問通告
1 重層的支援体制整備事業を視野に入れた地域共生社会への取組について
令和5年3月定例会の他会派による代表質問において、介護、障がい、困窮、ひきこもりなどの相談窓口の一元化や、総合相談窓口の設置など、より相談しやすく、分かりやすい体制の構築に向けた検討をして頂くとの答弁があったが、その進捗状況とともに、厚生労働省が提示している重層的支援体制整備事業の本市導入の可能性とその課題について伺う。
- ⑴ 総合相談窓口の設置計画のスケジュールと見通しについて
- ⑵ 重層的支援体制整備事業の実施に必要な既存事業と本市における実施状況について
- ア 介護、障がい、子供、困窮の各分野における相談支援の現状について
- イ 介護、障がい、子供、困窮の各分野における地域づくり事業の現状について
- ⑶ 属性を問わない居場所づくりにおける課題について
- ⑷ 重層的支援体制整備事業導入の可能性と課題について
2 中学校における情報教育について
情報技術の発展は目覚ましく、社会の形が大きく変革しつつある。そのような中、2020年には小学校でのプログラミング教育が必修化され、2021年より中学校で技術家庭でのプログラミングの内容が拡充、2022年より高校で情報Ⅰが新設・必修化されました。2025年には国立大学での受験科目に情報Ⅰが必須となるなど、情報教育を取り巻く環境も大きく変わろうとしている。そこで、本市における情報教育の現状について伺う。
- ⑴ 情報教育を担当する教員のスキルについて
- ⑵ 学習教材について
3 災害時の避難行動要支援者の避難と福祉避難所について
国立研究開発法人 防災科学技術研究所が運営している、地域防災webというインターネットサイトによると、本市の災害危険性は「30年以内に震度6弱の揺れに見舞われる確率」が高く、その他の災害は比較的低く評価されている。もし万が一、本市で全市的に避難所を活用するような事態の時は、近隣地域も同様の状態となり、物流や電力網などインフラに大きなダメージを被ると予測される。本市における防災計画は東海一円の甚大な災害を主眼とするべきであると考えるが、そのような状況では、消防や各種医療機関は混乱の渦中にあると予測される。避難に配慮や支援が必要な方々の避難計画と、福祉避難所について伺う。
- ⑴ 避難行動要支援者名簿について
- ア 現在の名簿記載状況について
- イ 名簿中、通常の方法では避難が困難な方の把握について
- ⑵ 避難行動要支援者への対応における医療機関等との連携について
- ⑶ 福祉避難所の運用方針について
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。