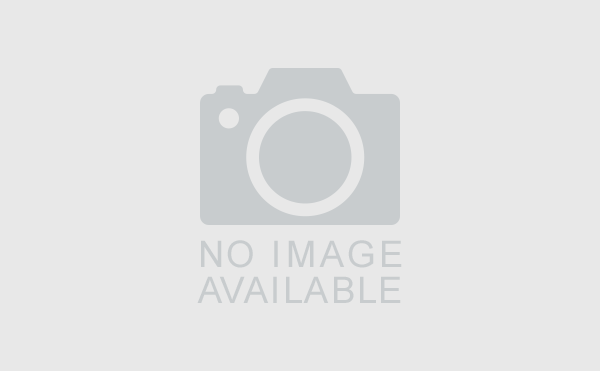災害時の避難行動要支援者の避難と福祉避難所について
◆1番(勝股修二) それでは、質問事項3に移ります。
災害時の避難行動要支援者の避難と福祉避難所についてに入ります。
質問に入る前に、本質問を行うに当たって本当にたくさんの資料を拝見いたしました。尾張旭市国土強靱化計画、尾張旭市地域防災計画、尾張旭市避難所運営マニュアルなどなど、非常に多くの分厚い資料が作成されており、これも日頃の危機管理課をはじめとした本市の職員の皆様の努力のたまものであると敬服をしております。
国立研究開発法人防災科学技術研究所が運営している地域防災Webというインターネットサイトによると、本市の災害危険性は30年以内に震度6弱の揺れに見舞われる確率が高く、そのほかの災害は比較的低く評価をされております。まさに柴田市長が所信表明で「地勢的に天の恵みと言えるほど自然災害に強い地域にあります」とおっしゃられたとおり、局地的な災害リスクはかなり低いのだと私も感じております。交通事情としては高速道路や基幹鉄道などが市内を走る、あるいは隣接するなどをしており、交通の要衝に近い立地です。もし万が一、本市で全市的に避難所を活用するようなときは、近隣地域も同様の状態となり、物流や電力網など、インフラに大きなダメージを被ると予測されます。つまり、本市における防災計画は、東海一円の甚大な災害を主眼とするべきであると私は考えます。そのような状況では、消防や各種医療機関は混乱の渦中にあると予測され、少なくとも数日間は過酷な状況にさらされると想定をする必要があります。そのような中、避難に配慮や支援が必要な方々の対応をどのようにしていくのか、検討してまいります。
⑴ 避難行動要支援者名簿について
ア 現在の名簿記載状況について
◆1番(勝股修二) 小項目(1)、避難行動要支援者名簿について、尾張旭市地域防災計画第2編第4章第2節(3)に避難行動要支援者名簿の整備が位置づけられていますが、ア、現在の名簿記載状況についてお伺いいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
名簿の記載状況につきまして、まず、令和5年4月時点の対象者数は1万3,472人です。
次に、記載項目は、対象者の住所、氏名、年齢、性別、生年月日のほか、避難支援を必要とする事由として、70歳以上の高齢者のみの世帯か否か、身体及び精神障害者手帳の等級数、介護度数、療育手帳の判定内容、障がい箇所などを記載しております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
現状、名簿には1万3,000人以上の方が名を連ねられているということです。本市の要介護者の人数が約3,800人であることを考えると、70歳以上の高齢者のみの世帯の方の人数はかなり多いと推測をいたしますが、70歳以上といっても、その方々の身体状況はそれぞれであって、日々スポーツに打ち込んでおられるような方も多くいらっしゃいます。これだけ多いと本当に支援が必要な方の把握がちょっと困難なのかなとも思いますが、それを踏まえて次の質問に入ります。
イ 名簿中、通常の方法では避難が困難な方の
◆1番(勝股修二) イ、名簿中、通常の方法では避難が困難な方の把握について、市として情報を把握しておられるのか、お伺いいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
先ほど答弁させていただいたとおり、名簿には避難行動要支援者の避難支援を必要とする事由を記載しておりますが、どのような避難支援が必要かまでは記載しておりません。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
避難支援を必要とする事由は記載してあるが、個別具体的なその理由までは記載はしていないということでした。これだけ人数が多くて、実効性のある情報は記載していないのであれば、なかなかちょっと役に立つことの少ない名簿であるなといった印象ですけれども、地域防災計画に位置づけられている名簿ですので、こちらについても国土強靱化計画にPDSサイクルを回して、常に改善をしていくというところが位置づけられておりますので、評価・見直しをしていただいて、実効性のある名簿になるようにぜひ御検討をお願いいたします。
尾張旭市避難行動要支援者支援実施要綱には、避難支援等関係者が災害時の避難誘導、救出救助、安否確認等を行うとなっておりますが、その避難支援等関係者とは、自治会、町内会、自主防災組織、民生委員、児童委員及び近隣者等とされております。かなり自助・共助・公助の点でいくと、共助の部分がかなり避難支援等関係者のところかと思いますが、ただ、生命維持に電源を必要とする方など、医療依存度の高い方の避難はかなり特殊であります。通常の方法では避難が困難であると考えられ、平時のうちから消防や各種医療機関と連携をして、災害時の対応や情報の連携方法などを把握しておくことが必要ではないでしょうかという考えを述べた上で、次の質問に移らさせていただきます。
⑵ 避難行動要支援者への対応における医療機関等との連携について
◆1番(勝股修二) 医療技術の発展や介護保険、障がい福祉制度などにより、人工呼吸器などを使用されている様々な状況の医療依存度の高い方が御自宅での生活をしていただけるようになってきましたが、先ほどの質問にありましたように、医療依存度の高い方の避難行動には特殊な支援が必要になってくると考えられ、自分や家族で何とかする自助や自治会や近隣の方々の力をお借りする共助ではなかなか難しい方もいらっしゃいます。有事の際には様々な状況が生じてくると考えられ、状況が目まぐるしく変化して、消防や医療機関等がすぐには対応できないような状況が発生する可能性もあります。その際には優先順位をつけて、順次対応していく必要がありますが、医療依存度の高い方には一定のタイムリミットがあります。医療機器等にも様々な特性があり、一例として、人工呼吸器のバッテリーは2から6時間、外部バッテリーを用意しても最大22時間程度しかもちません。手もみ式のアンビューバッグを使用すれば、生命維持は何とか可能ですが、それでも、できるだけ時間内に対応する必要があります。しかし、そのタイムリミットについて把握をしていない状況では、有事の際にはどのような状況になってしまうのかを危惧しております。その対応について、平時のうちにできるだけ協力機関と情報の連携と有事の際の対応を検討しておくことが必要かと考えます。
そこで、小項目(2)、避難行動要支援者への対応における医療機関等との連携について、現状どのような連携が取れているのか。また、今後どのような連携を模索されていくのか、お伺いをいたします。
◎総務部長(三浦明) お答えをします。
まず、避難行動要支援者とは、災害が発生もしくは発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な方であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要する方であります。
災害時、この支援を要する方、避難行動要支援者への対応をより一層スムーズに進めるための医療機関等との連携につきましては、災害時の医療救援に関する協定を締結している瀬戸旭医師会を中心とし、各関係機関への受入れ調整などの対応を迅速に進める必要があると考えております。
そのため、現在は総合防災訓練への参加をはじめ、平時からの良好な関係づくりを進めております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
瀬戸旭医師会をはじめ、関係各所との連携、関係づくりを進めていただいているということでありがとうございます。
ちなみに介護事業所では、令和3年には業務継続計画BCPの作成が義務化をされました。居宅介護支援事業所においては、BCPガイドラインにおいて災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あらかじめ検討の上、利用者台帳等においてその情報が分かるようにしておくこととして留意する点が明記をされております。優先的な安否確認が必要な方については、居宅介護支援事業所がしっかり把握をされております。避難行動要支援者への対応と情報収集については、行政だけではなかなか難しいと思いますので、地域に根づいている介護支援事業所等との連携についても御検討いただいた上、消防や救急等との情報の連携、避難支援のシミュレーションなどの御検討をお願いいたします。
ちなみに、もうすぐ何か瀬戸のほうで、ちょっとそういう瀬戸旭医師会さんと地域の医療の専門職等で、いろいろそういうシミュレーションというか、検討するみたいなこともありましたので、尾張旭のほうでも進めていただけるといいと思います。
⑶ 福祉避難所の運用方針について
◆1番(勝股修二) では、次の質問に移ります。
本市には災害時の福祉避難所として保健福祉センターが指定され、そのほか協定社会福祉施設と--これは老人保健施設や特別養護老人ホームとかになりますね--が10か所設置をされています。特に保健福祉センターには非常用電源等を設置されており、ライフラインが途絶するような大規模災害時には、在宅人工呼吸療法や在宅酸素療法などを必要とする方の一時的な拠点になる可能性があると考えますが、小項目(3)、福祉避難所の運用方針についてお伺いをいたします。
◎総務部長(三浦明) お答えいたします。
福祉避難所につきましては、高齢者や障がいのある方など、避難所生活において特別な配慮を必要とする方のために開設される避難所であります。
本市では保健福祉センターを福祉避難所として指定しております。
現在、福祉避難所としての機能がスムーズに果たせるよう関係部署による検討会を開催しております。この検討会の中で様々なケースを想定し、一つ一つの課題をクリアし、避難生活において特別な配慮を必要とする方が安心して生活できるよう体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 関係部署で検討会を開いていただいて、課題を一つずつクリアしていただいて、特別な配慮を必要とされる方が安心して避難所生活を送っていただけるように御尽力をいただいているということでした。私が理学療法士として各家に訪問でお伺いしていたときに、やっぱり人工呼吸器を使ってみえた御本人や御家族の方、災害のとき、それこそ、それは東日本大震災のころだったので、こういう災害起きたらどうしますかという話をちょっとさせていただいたときに「もうそんなときは諦めるよ」と、「そんな避難所に行くよりも家にそのままいて、このまま最期を迎えるほうが私はいいわ」みたいな感じで、「もう本当に災害時どうなるか分からない、不安が大きいので、もうそのまま家で過ごしていきたい」みたいなことを言ってみえた方がみえました。本当、それを思い返すと、なかなかそれについて行政としてとか医療職として、安心をちゃんと感じていただけてないということに非常にちょっと心苦しい思いをしていたんですけれども、そういう諦めるみたいなことがないように、市として、そこについてしっかり検討していただいて、安心して避難所生活を送っていただけるようにまた皆さんにお伝えをしていただければと思います。
再質問)福祉避難所について検討する関係部署とはどのような部署か
◆1番(勝股修二) ここで、再質問をお願いします。
検討会を開かれている関係部署とは、どのような部署でしょうか、お伺いをいたします。
◎災害対策監兼危機管理課長(浅見行則) お答えします。
福祉避難所における受入れ体制や受入れ対象者、移送方法などの課題について検討を進めている関係部署は、福祉課、長寿課、健康課及び危機管理課の4課でございます。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
福祉避難所の運用に向けて、様々な部署が協力をしていただいているということです。
再々質問)関係部署に社会福祉協議会を加えることについて
◆1番(勝股修二) しかし、福祉避難所の実際の運用について考えますと、特別な配慮が必要ということで医療や介護の専門的な知識を持ち合わせている方々の御協力は不可欠と考えます。その点、福祉避難所として指定をされている保健福祉センターに業務の本拠を置いている尾張旭市社会福祉協議会さんが関係部署に入っていませんでした。関係部署というのは、市役所内の部署ということだと思うんですけれども、かなり近いところにある社会福祉協議会さんが入っていないということで、福祉避難所の運用には保健師や介護の専門家を擁する地域包括支援センター、社会福祉協議会さんに御協力していただくようお願いしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
再々質問をお願いします。
◎災害対策監兼危機管理課長(浅見行則) お答えします。
地域包括支援センターなどの業務を請け負っている社会福祉法人尾張旭市社会福祉協議会が検討会に参加していただくことは、福祉避難所の体制や機能をスピーディーに構築するために、大変有意義なことであると思います。まずは、社会福祉協議会の参加に向け、調整を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
社会福祉協議会さんとは、様々な分野で協力・連携しているとは思いますが、ぜひ防災・減災分野においてもさらなる連携を深めていただきますようお願いいたします。
最後に、今回の個人質問は、福祉、教育、防災の3つの分野に分かれましたが、共通したテーマは官民連携です。
質問事項1は地域の住民、事業者と、質問事項2は知見を集約した全国的企業と、質問事項3は地域の専門的な事業者との協力・連携です。何度もお伝えをしているとおり、個人あるいは小さい単位での取組では、なかなかやっていけない時代が到来をしているのだと思います。
民間出身の柴田市長は、官民連携を重視しておられると聞き及んでおります。今後もさらなる官民の協力を推し進めていただきますよう切にお願いして、私の一般質問を締めくくらさせていただきます。どうもありがとうございました。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。