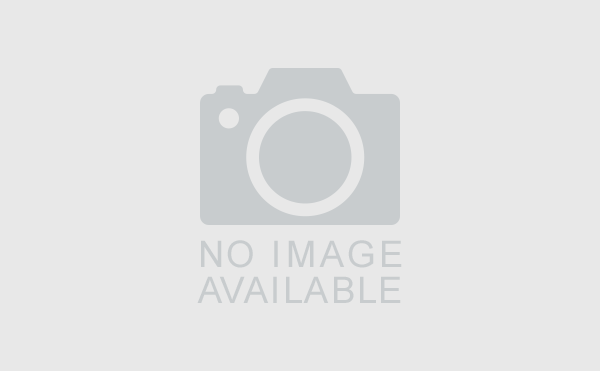自治会とその入口としての市民活動について
◆1番(勝股修二) それでは、質問事項2、自治会とその入口としての市民活動についてに入ります。
自治会加入率の改善に対して、様々な検討がなされていますが、残念ながら自治会への加入率は年々低下傾向となっています。これは全国的な傾向で、近隣市町においても同様のようです。第六次総合計画においても、自治会・町内会加入世帯数の将来指標を2万1,129世帯と、現状維持を目標とされています。
自治会などの地域活動は、防災や防犯、ごみの収集、親睦など、非常に重要な機能を持っていますが、その重要性の認識については、なかなか広まらないというのが現状です。
しかし、自治会制度は、地縁や血縁などにより、既に関係性の深いコミュニティーで生まれて、家族の中で働き手が1人いれば、家族を養っていくことができる時代に、その変遷をたどってきた制度であり、時代に合わなくなっているのも実情であると考えます。
自治会の催しは土日に多くて、土日祝休みの方というのは、日々の仕事に手いっぱいで、休日くらいは休ませてほしいとか、そういう気持ちもよく理解できますし、働き方の多様化により、土日祝はお休みでない方も多くいらっしゃいます。
しかし、内閣府による調査では、社会活動への参加に対する国民の意識というのは、社会の人間関係の希薄化が言われる中にあっても、6割以上の国民、63.4%の国民が、社会貢献の意識を持っており、その意識を行動につなげるきっかけづくりが必要とされています。
そこで、比較的若い世代の自発的な市民活動を支援することで、自治会加入の入り口となる可能性を模索するべく、本市の現状と考え方について伺っていきます。
まずは、解決策を探るには、現状分析が必要だと思います。昨年3月にも同様の質問があったと思いますし、昨日も少し話が出ていました。
⑴ 自治会の現状について
ア 加入率について
◆1番(勝股修二) 小項目(1)、自治会の現状について、ア、加入率について、最新の情報をお伺いできたらと思います。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
令和5年度の自治会加入率は57.19%で、令和4年度と比較しますと1.29ポイント減少しております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
やはり右肩下がりで下がっているということですし、少し前回よりポイントが開いています。
イ 目標値とその考え方について
◆1番(勝股修二) 先ほどお伝えしたように、第六次総合計画において、目標値が現状維持ということになっていますけれども、イ、目標値とその考え方について、お伺いできたらと思います。よろしくお願いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
コミュニティー活動を取り巻く環境は、少子化・超高齢社会の到来による世帯構成の変化、雇用年齢の引上げ、生活スタイルの変容等により多様化しており、自治会加入率は全国的に見ても減少傾向にあります。
目標値としましては、実数である加入世帯数に着目し、現状の数値が低下しないよう自治会活動の必要性を周知するともに、役員負担の軽減等に取り組んでまいります。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
世帯構成の変化や生活スタイルの変容など、社会構造の変化により、旧来の制度がきしみを上げているというのは、共通の理解だとは思います。
事前にいただいた数字を見ますと、総世帯、令和4年度が3万6,665世帯、令和5年度3万6,947世帯と、282世帯増えているのに対して、自治会の加入世帯は、令和4年度2万1,443世帯、令和5年度2万1,129世帯と、314世帯減少してしまっています。
正確な表現ではないかもしれませんが、令和5年は約600世帯の方が引っ越してきたけれども、自治会に入らない。あるいは加入していた方が自治会を退会されるとの判断をされたということで、加入者数を増やすどころではなくて、現状維持を目標とせざるを得ない危機的な状況であるということだと思います。
御答弁にて、役員負担の軽減に取り組んでいくということを示していただきましたが、自治会の業務負担により、役員の成り手がいないなどの問題を生じさせていることは明白だと思います。
ウ 自治会における業務負担の軽減について
◆1番(勝股修二) では、これまでどのようなことが自治会業務負担の軽減として検討されてきたのか、あるいは、実施されてきたのか、現状をお尋ねします。
ウ、自治会における業務負担の軽減について、お伺いしますが、こちら昨日の質問でも同じようなところがありましたので、重複するところは省略していただいて大丈夫ですので、お願いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
自治会活動では、役員の担い手不足が問題になっていることから、今年度は助成金の申請手続を電子化したほか、初めて自治会向け地域活動ICT支援講習会を実施するなど、デジタル化による負担軽減に着手しております。加えまして、役員のモチベーションを上げるようなインセンティブに関する取組を研究しているところでございます。
また、各自治会でも役員に負担が集中しないよう、有志による防災対策班を組織したり、自治会内の健康体操グループが主体となって活動をしたり、会費の戸別徴収を民間に委託するなど、様々な取組事例がありますので、こうした情報を広く周知し、自治会における業務の負担軽減を支援してまいります。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
負担を軽減するとともに、モチベーションを上げるインセンティブも研究をしていただいているということです。また、有志による自発的な活動を後押しして、自治会の負担を分散していくということです。
エ 自治会・町内会活動に関する調査結果の受け止めについて
◆1番(勝股修二) では、当事者の方々はどのように考えているか見ていきますと、本市の自治会・町内会活動の現状については、昨年3月にアンケートの調査結果が公表をされています。対象者は自治会や町内会の会長ということで、自治会や町内会の必要性を理解されており、活動に対して肯定的な方々のはずです。
しかし、本アンケートにおいては、自治会は今のままでは立ち行かなくなることや、自治会、町内会そのものの必要性や存続について検討するべきとの御意見もあります。このアンケートに対して、本市はどのように受け止められておられますでしょうか。
エ、自治会・町内会活動に関する調査結果の受け止めについて、お伺いをいたします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
令和4年度の自治会長、町内会長に行った自治会・町内会活動に関するアンケートでは、地域のつながりを実感できたなどの肯定的な意見もありましたが、自治会活動の効率化や簡素化を願う意見、未加入者や退会者への不公平感、役員負担に対する不満、役員の成り手不足などの課題のほか、自治会の存続自体を危ぶむ厳しい意見等がありました。市民の皆様の自治会活動に対する率直な意見として捉え、重く受け止めております。
今後もそうした意見を踏まえ、負担軽減やインセンティブの付与などの取組を継続的に研究し、自治会活動を支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
ここでも負担軽減やインセンティブの付与について言及をしていただきました。
しかし、率直に言いますと、小手先の対応ではなかなか難しいのではないかなというのが現状で、今後、行政の役割と自治会の役割の整理や線引きなど、地域の方々としっかり話し合う必要があるのではないか。現在、自治会の役割とされていることを、一定程度、行政が引き受けていくことも、検討をする必要があるのではないでしょうか。
未加入者や退会者への不公平感があると、先ほど言われましたけれども、この問題は全国的に噴出をしていまして、特にごみ捨場の問題については、様々なところで裁判中、係争中であります。市民が助け合う場である自治会が、争いの場になってしまう前に、手だてを打っておく必要があるのではないでしょうか。
⑵ 自治会やPTAへの参加における地方自治体の地域貢献活動休暇について
◆1番(勝股修二) 次が、小項目(2)に移ります。
自治会活動についてなんですが、先日、読売新聞で、「公務員の地域貢献には休暇OK、総務省が自治体に通知…自治会・NPO・PTAなど想定」との記事が出されました。記事では、地方自治体は、条例を定めるなどすれば、職員の特別休暇として、地域貢献活動休暇を新たに創設をできると。自治会やNPOなどの担い手不足が地方で深刻化する中、兼業などによる職員の地域活動参加を促す狙いがあるとされています。
この記事は、様々な議論を経て、昨年12月に総務省より発出された、「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」の結果等を踏まえた地方公共団体における勤務環境の整備・改善等についての通知に関することであると推測しますが、これらに対して小項目(2)、自治会やPTAへの参加における地方自治体の地域貢献活動休暇について、本市の見解をお伺いします。
◎企画部長(松原芳宣) お答えします。
地域社会に貢献する活動に従事するための特別休暇を創設することは、働く世代の地域活動参加を促進する社会的風潮の醸成や地域活動の担い手不足の解消の一助となる効果が期待されます。
一方で、職員は公務を優先することが原則であり、勤務を欠くことの妥当性を慎重に判断する必要があります。
いずれにしましても、まだ示されたばかりの考え方であり、他市の動向なども参考にして、研究してまいりたいと考えます。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
国の示した方針であって、現状ではちょっと評価も難しいかと思います。
総務省は、こうした動きが広まれば、担い手不足の解消とともに、職員が地域活動の実態を知ることにもつながると期待をしているとしていますけれども、既に本市職員は、様々な地域活動に関わっていて、自治会というのは、もう本市職員のOB、OG会のようになっているところもありますし、PTA会長、うちの校区などだと、本市職員の充て職みたいな感じになってしまっているところもあります。
退職者ならまだしも、本市の指揮命令下にある現職の職員が、休暇を使って、自治会・町内会役員までやらなければいけないとなると、それは地域の住民が自主的につくり上げる住民自治組織なのでしょうかというところです。
⑶ 文化会館における市民活動において、営利と判断される基準について
◆1番(勝股修二) では、そこで小項目(3)に移ります。
以上のように、自治会・町内会の加入率低下の問題は、全国的な問題であり、国の方針もいま一つ疑問の残るものです。そこで、自治会・町内会だけで考えるのではなくて、もっと視野を広げて市全体を見渡すことも必要になるかと思います。
昨年の6月定例会代表質問において、新城市の若者議会の質問が少し出ていましたが、答弁としては、若者の意見を聴くとか、意見を反映していくということで、要望型の域を出ませんでした。
しかし、新城市の取組は、要望型の関わりを目指しているのではなくて、参加型の関わりを目指しています。若者議会というのは1,000万円の予算をつけて、若者の提案を実現をさせることにこだわって、主体的、自発的な関わりをいかに促すかというところです。そのほかのまちづくり、地域づくりについても、市民まちづくり集会など、自発的な参加を促すことを目的にした施策となっています。
そこで、本市においても、市民の自発的な関わりをいかに増やしていくのか、入り口の一つとして、市民活動から考えていきたいと思います。
市民活動を維持運営していくに当たっては、その活動内容にもよりますが、ある程度の活動資金が必要となります。活動に参加したい、続けていきたいというモチベーションをつくるためには、ちょっと特別なことをしているという思いも重要な要素だと思います。楽しさを加えるというところです。少しばかりであれば、自腹を切ってやっていこうということにもなりますが、特別感のあるイベントなどを運営していこうとなると、しっかりと活動資金を集めていかなければなりません。
本市文化会館では、実務上1,000円以上の入場料を集めること、あるいは物の販売を行うことなどが営利となる基準であることが、平成28年12月定例会の質問にて明らかになっております。営利かどうかの判断基準については、答弁において、「もう少し詳細な内容を調査し、今後、情報収集に努めながら、文化会館の設置目的であります、市民の文化、教養及び福祉の増進を図るため、ふさわしい内容を検討していきたいと考えております」とのことでしたが、約7年経過して、今、物価も高騰しております。その考え方に変化はありましたでしょうか。
小項目(3)、文化会館における市民活動において、営利と判断される基準についてお伺いをします。
◎教育部長(山下昭彦) お答えします。
現在、文化会館においては、1,000円を超える入場料を集める催しや、物品の販売等を伴う催しは、営利目的の利用として判断し、通常の3倍の利用料を設定しております。
なお、以前の市議会で御質問いただいた後、ほか自治体での判断基準について確認したところ、本市と同様、入場料の額や物販の有無を基準としている場合が多く、その内容の適否に関してはそれぞれ一長一短あるような状況でございました。
このため、現時点では、考え方の見直しまでには至っておりませんが、昨今の社会経済状況等を勘案しますと、基準としております入場料の額1,000円につきましては、見直す時期にあるのではないかと感じております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
入場料の額は見直す時期に来ているとお感じとのことです。市民活動団体の自発的な活動を維持していくためには、活動費の確保については避けては通れない問題です。
文化活動はインターネットや物流、人流の変化により、そのありようは変化をしています。経費をかけて本格的な催しをするような団体が増えていて、非常に多くのイベントが開催されていることから、ある程度特別なことをしないと、集客も困難な状況です。そのような状況で、入場料が制限をされて、活動費が不足するから、オリジナルグッズ売ってちょっと足しにしようというようなことをすると、営利とみなされて、利用料が跳ね上がる。このような様々な規制や障壁によって、工夫をしようと思っても、工夫もできない状況にあります。
市民の自発的な活動を促すためにも、制度を見直すに当たっては、問題が起きないように事なかれ主義で検討するのではなくて、どうすれば市民の文化活動を促進できるかの視点を持って検討していただけるよう、強く要望をいたします。
⑷ 経済的に自立した市民活動団体となるための具体的な方法について
◆1番(勝股修二) 次の小項目に移ります。
本市の市民活動促進助成金に、はじめの一歩部門があって、その要件に、設立3年未満の市民活動団体が成長し、経済的にも自立した事業展開を図るための事業とありますが、設立3年経過後に、経済的に自立するための具体的なビジョンというか、方策論というのを本市として持って、市民活動団体を支援するようなことはできているでしょうか。
小項目(4)、経済的に自立した市民活動団体となるための具体的な方法について、お伺いをいたします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
市民活動団体が経済的に自立するためには、活動資金の安定した収入が欠かせないと考えます。そのため、本市では助成金の案内、市民活動講座の開催、市民活動・NPO相談などを行っております。
助成金の活用につきましては、市民活動促進助成金のほか、国や県、法人などによる助成金の情報提供を行っております。
市民活動講座につきましては、市民活動支援センターにおいて、様々な講座を行っており、資金獲得をテーマとした講座も行っております。
市民活動・NPO相談では、専門家による資金の獲得も含めた市民活動・NPOに関する悩みなどに対応する相談を行っております。
このほか、市民活動支援センター登録団体については、会議室やプロジェクター等の備品の無償貸出しやコピー機、印刷機を安価に利用していただくことにより、活動費の軽減につながるよう支援をしております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
様々な支援を行っていただいておりますが、いささか助成金のウエートが高いようなところも感じます。自発的な活動を継続していくためには、やはり市民活動団体自身が、収益事業などを通じて自立をしていくということが重要だと考えますので、市としても自立に向けた具体的なビジョンや方法論というのを持っていただいて、支援あるいは制度設計をしていただけたらと思います。
⑸ 市民活動団体と自治会の連携について
◆1番(勝股修二) 最後の小項目に移っていきます。
市民活動を運営していると、徐々につながりがやはり生まれてきます。私の関わっている団体でも、イベントのときにコラボできないかとか、こんなものが必要なんだけれども、どこかの団体に御協力いただくことはできないかなとか、自然発生的につながりが生まれてきます。そうすると参加者の中におのずと地域への所属意識が生まれてこないでしょうか。
市としてそのようなつながりを後押ししていくような、特に市民活動団体と自治会・町内会のつながりを持てるような場というのは、現在ありますでしょうか。
小項目(5)、市民活動団体と自治会の連携についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
各連合自治会では、地域のコミュニティー活性化や防災、防犯等のために、様々な事業を行っております。例えば、地域の高齢者の長寿をお祝いする敬老イベントでは、中高生による音楽演奏や、専門家による健康に関するアトラクションなどが企画されております。
こうした行事に、芸術、文化、スポーツ等を得意とする団体や、保健、医療、福祉等を活動分野とする市民活動団体に御協力いただくことで、連携を深め、若い世代にも自治会活動を知っていただき、自治会加入のきっかけとしていくことが可能と考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
市民活動団体との連携というのが、自治会加入のきっかけとなり得ることについて、共有をしていただけたと思います。
自治会に関する先進事例を調べてみますと、まちづくりに関する市民活動団体やNPOとの協働が一つのキーワードになっています。自治会に若い方々の参画を促していくためには、まずは若者たちが楽しいこと、面白いことというのを、自由にできる環境づくりというのが必要ではないでしょうか。
戦国時代から江戸時代にかけて、各地の戦国大名が、自分の領地を繁栄させるために行った経済政策として、楽市楽座というのがあったことは、皆さん御存じだと思います。人の活動を活発化させることには、様々な規制を緩和をすることが重要であることは、戦国時代からもう分かっていることです。
規制は、国民の安全のためにその都度整備されてきたものではありますが、本当に様々な規制が絡み合い、複雑化して、市民の活動を抑制をしてしまっているようなところもあります。規制を取り払うのは、地方自治体レベルではなかなか壁の高いものではありますが、現行規制の中でもできること、またできないことというのを明確化をして、市民活動をやりやすい方向に施策を向けていくのも、現在必要とされていることだと考えます。
なかなか市民活動をやっているに当たって、収益活動をしていると、これやっていいのかな、これやっては駄目なのかなというところは、非常に曖昧なところがあって、なかなかそのたびに立ち止まるなどということもありますので、そこのところはきちんと明確化をしていただくようなことを考えていただければと思います。
活発になった市民活動団体が、市全域のネットワークを形成して、自治会の働きを補完することで、全市の福祉が向上することを祈りまして、私の質問を締めさせていただきます。
今回も質問に当たり、多くの市民、事業者、市民活動団体さん、職員の皆様に御協力いただけましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。
最後に、3月末で勇退される方々に、私本当に、11か月しか一緒に仕事ができなかったんですが、特に河村教育長には、ずっと真ん前の席でということで、本当にいつも顔を合わせて、議会に出ていることを思い出されます。ということで、皆さんのバトンを受け継いで頑張っていきたいと思いますので、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。