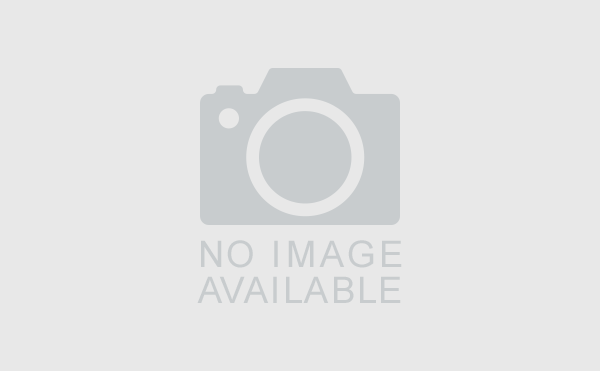重層的支援体制整備事業を視野に入れた地域共生社会への取組について
◆1番(勝股修二) それでは、よろしくお願いいたします。愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
ただいま、議長よりお許しがありましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。
早速質問事項1に入っていきます。
重層的支援体制整備事業を視野に入れた地域共生社会への取組についてとなります。
まずは、余談で、ちょっとこう込み入った話なので流していただいていいんですが、業務を改善していくためのPDCAサイクルが普及して久しくなりました。近年ではPDCAサイクルは古くなってしまったと言われていますが、これはサイクルを回すのに時間がかかり過ぎて、変化の波が激しい現代社会においては適切ではないということです。
それに対し、OODAループといった、観察して、状況判断して、決断して、行動するという一連のサイクルをループ状に回していく方法や、PDRサイクルといった準備して、実行して、評価するというPDCAサイクルを速く回すようなフレームワークも普及してきています。
どれを使用するにしても、大事なのは目標設定ですが、目標設定にも様々な法則があります。その1つに、SMARTの法則というものがあり、目標はSpecific、具体的であり、Measurable、計測可能であり、Achievable、実現可能性があり、Relevant、組織の目標と関連性のある、Time-bound、期限を切ったものであるかが重要になります。ただ、この法則は提唱されて40年以上たっていることから、古いだったり、時代遅れであるといった指摘もされているんですが、FASTの法則といったものも使われるようになってきています。
いずれにしても、組織を動かしていくためには、明確で期限を切った目標を設定をしていくことが重要となります。
⑴ 総合相談窓口の設置計画のスケジュールと見通しについて
◆1番(勝股修二) 令和5年3月定例会の他会派による代表質問において、「介護、障がい、困窮、ひきこもりなどの相談窓口の一元化や、総合相談窓口の設置など、より相談しやすく、分かりやすい体制の構築に向けた検討」をしていただくとの御答弁がありました。そこで、半年経過した現在、小項目(1)総合相談窓口の設置計画のスケジュールと見通しについてお伺いいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
今し方議員が述べられたとおり、令和5年3月定例会の代表質問において、「相談窓口の一元化や総合相談窓口の設置など、より相談しやすく、分かりやすい体制の構築に向けた検討を今後進めていきたいと考えております。」と市長が答弁をいたしました。
このことを受け現在、福祉政策課において、福祉部門の総合相談窓口である「福祉相談窓口」の設置に向けて検討を進めているところでございます。なお、本件のスケジュールと見通しにつきましては、福祉相談窓口を設置するに当たり、相談窓口の3つの柱である生活困窮者相談窓口の「自立相談支援機関」、障がい者相談窓口の「基幹相談支援センター」、そして高齢者相談窓口の「地域包括支援センター」が一つに集約できるスペースの確保という課題がありますので、全庁的な組織検討と連携しながら進めてまいります。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございました。
総合相談窓口の設置や体制の構築などは、スペースの確保や全庁的な組織検討が必要とのことで、期限も区切れずなかなか進んでいないのかなと正直感じております。
小項目(2)に移ります。
⑵ 重層的支援体制整備事業の実施に必要な既存事業と本市における実施状況について
ア 介護、障がい、子供、困窮の各分野における相談支援の現状について
まずは、地域共生社会を実現するために制度化されている重層的支援体制整備事業について、少しだけ説明をさせていただきます。
平成29年の社会福祉法改正により、地域福祉推進の理念が規定され、これを実現するために、市町村は「包括的な支援体制」づくりに努める旨が示されました。次に、市町村において「包括的な支援体制」の構築を推進するための事業として、令和2年の同法改正によりこの事業が創設をされました。
この事業を紹介する厚生労働省のホームページには、「日本の社会保障は、人生において典型的と考えられる課題の解決を目指すという、基本的なアプローチの下で発展してきました。このため、日本の福祉制度・政策は、子ども・障がい者・高齢者といった対象者の属性や要介護・虐待・生活困窮といったリスクごとに制度を設け、現金・現物給付の提供や専門的支援体制の構築を進めることで、その内容は、質・量ともに充実してきました。一方で、人びとのニーズに目を向ければ、例えば、社会的孤立をはじめとして、生きる上での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくいケースや、いわゆる「8050」やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わっていくことが必要なケースなどが明らかとなっています。このような困難・生きづらさの多様性や複雑性は、以前も存在していました。しかし、かつては、血縁・地縁・社縁などの共同体の機能がこれを受け止め、また、安定した雇用等による生活保障が強かった時点では、福祉政策においても強く意識されてこなかったのだと考えられます。」とあります。
本市の現状を見ますと、令和5年6月定例会にて他会派の議員が発言されたとおり、血縁・地縁を持った古くから住んでおられる方々がマイノリティーとなってきています。また、第六次総合計画策定に向けたパブリックコメントの計画素案において、従業者の65%が市外で働いており、これは新たな転入者に限って言うとさらに割合が増える可能性もあります。つまり社縁についても、距離的にもともと薄い上に、定年後はさらに薄くなってしまうと推測されます。
つまり本市の市民は、血縁・地縁・社縁による共同体の機能がさらに機能しなくなっていくのではないかと危惧をしています。私自身、他県出身者であり、勤務先はほとんど他市、通勤には1時間以上かかる遠方でした。議員に転身したことから、地域のつながりもある程度はできてきましたが、前の職場に定年まで勤め上げていたとしたら、地域のつながりができていたのか非常に不安を感じました。また、私は、就職氷河期世代です。まさに非正規職員が増えていった時代を生きてきたわけで、安定した雇用等による生活保障もかなり弱まってきています。
以上のことからも、これからも本市市民が安心して暮らしていくための地域共生社会を実現するためには、参加支援や地域づくりにより一層力を入れなくてはいけないと考えます。それらの施策をより一層充実させるために、厚生労働省において制度設計をされたのがこの事業ですが、小項目(1)において計画をお伺いした総合相談窓口は、この事業にある程度近い考えのものだと思います。この事業は既存の相談支援事業と地域づくり事業に加えて、新たな事業を加えていくことが求められています。
今後、この事業に手を挙げることができるかどうかを検討していくためにも、小項目(2)、重層的支援体制整備事業の実施に必要な既存事業と本市における実施状況について、ア、介護、障がい、子供、困窮の各分野における相談支援の現状についてお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
重層的支援体制整備事業の実施に必要な事業として、相談支援に係る事業が、社会福祉法第106条の4第2項中、4つの分野で定められております。
現在、介護の分野では、地域包括支援センター運営の「地域支援事業」、障がいの分野では、障がい者基幹相談支援センターの「障害者相談支援事業」、子どもの分野では、あさぴー子育てコンシェルジュの「利用者支援事業」、困窮の分野では、生活困窮者相談支援の「生活困窮者自立相談支援事業」をそれぞれ実施しているところです。
答弁は以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
相談支援事業はしっかりと整備をされていることが分かりました。
イ 介護、障がい、子供、困窮の各分野における地域づくり事業の現状について
◆1番(勝股修二) 次に、この事業に求められるもう一つの既存事業、イ、介護、障がい、子供、困窮の各分野における地域づくり事業の現状についてお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
地域づくりに係る事業も同じく社会福祉法にて5つの事業が定められております。
現在、介護の分野では、らくらく筋トレグループ支援の「一般介護予防事業のうち地域介護予防活動支援事業」、また、あさひ生活応援サービス事業の「生活支援体制整備事業」、障がいの分野では、障がい者のデイサービス的役割の「地域活動支援センター事業」、子どもの分野では、子育て支援センター運営の「地域子育て支援拠点事業」の4事業を実施しておりますが、困窮の分野での「地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」につきましては、現在、実施に向けて情報収集を行っているところでございます。
以上です。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
御答弁にありましたように、この事業に求められる既存事業は、本市においても困窮分野の地域づくり事業以外のほとんどの部分は既に実施済みであります。この事業に手を挙げるためには、新規の事業、既存の支援施策では対象となってこなかったような方への伴走的支援や、アウトリーチ型支援、居場所づくりなど、本市の実情に合った事業を考えていくことが必要かと思います。
⑶ 属性を問わない居場所づくりにおける課題について
◆1番(勝股修二) そこで、小項目(3)に移ります。
現在、本市では、サロン、健康づくり事業、認知症カフェなど様々な施策が展開されていますが、これらの事業においては国や県からの補助金の性質から対象者を限定する必要があるかとも思います。本市の各種団体の皆様や、高齢者事業を展開されている経営者の方々には、子供や若い世代と高齢者など多世代が交流できる場を創出したいと考える方が多いですが、制度の壁に阻まれてなかなか実現できないとの御意見を頂戴することもままあります。
高齢者にとって若い世代と交流することは、精神的な活性化につながり、認知機能へのよい刺激となります。また、若い世代が高齢世代と交流することは、ためになる知識や知恵を得られる、他者とのコミュニケーション能力を向上できるなどの効果が期待されます。多世代の交流は、つながりのある地域、お互い助け合える地域をつくっていくのに非常に重要であると考えます。介護、障がい、子供、困窮などの属性を問わない居場所づくりは、今後の地域共生社会にとって非常に重要な施策と考えますが、これまでの既存の社会福祉政策では、なかなか壁が高いと感じます。
そこで、小項目(3)、属性を問わない居場所づくりにおける課題について、本市のお考えをお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
属性を問わない居場所づくりは、血縁・地縁・社縁といった共同体機能が脆弱化する中、地域の課題の掘り起こしや困り事の解決に直結する福祉的な活動だけではなく、「楽しそう」、「面白そう」といった興味・関心から地域における多様なつながりが生まれ、人と人、人と地域がつながり支え合う、いわゆる「緩やかなつながり」による見守りなどの充実を図っていくものです。
この取組を進めるに当たっては、定期的に属性を問わない居場所を提供していただける受皿をどのように確保するかが課題であると考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
属性を問わないということでしたので、補助金の取扱いなどの難しさなどあるのかと考えていましたが、予算面ではあまり課題を感じていないのかなと受け取りました。しかし、実際に居場所を提供していただける人手、場所の確保が課題であるとの御認識であるということが分かりました。
重層的支援体制整備事業は、まさに地域の住民、事業者、行政職員の皆さんとの地域共生社会の実現に向けての機運をいかに醸成していくかが鍵になると厚生労働省の方にお聞きしました。居場所づくりに必要な場所や人手を確保するには、住民や事業者の皆さんが、官民連携の上、主体的に動いていただけるよう働きかけていくのが、議員や行政の役割なのかなと思います。
小項目(4)に移ります。
⑷ 重層的支援体制整備事業導入の可能性と課題について
◆1番(勝股修二) 厚生労働省が提案する重層的支援体制整備事業は、これから地域共生社会を実現していくに当たって一つの選択肢となり得ると考えます。この事業は、既存の事業に対する補助金額を維持した上で、参加支援などの新たな事業に追加の交付金がつきます。また、それらの補助金の壁をなくし、包括的に交付することで、本市の裁量が増し、本市の実情に応じてより一層工夫をしていくことができると考えられます。
近隣自治体においても、お隣の長久手市は制度創設前より先進的に取り組んでおり、全国的なモデル自治体にもなっています。また、本年度には、豊明市、大府市、春日井市など、近隣市町に加えて、愛知県内では既に54自治体中14自治体が実施をしており、そのほかにも名古屋市を含んだ7自治体がこの事業の導入に向けて移行準備事業を行っています。また、お隣の瀬戸市も導入に向けて人員を配置し、住民の機運醸成を図っているとのことでした。
そこで、小項目(4)、本市が制度導入の可否を検討するに当たっての重層的支援体制整備事業導入の可能性と課題についてお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
近年、我が国では、少子超高齢化、人口減少、核家族化、社会構造の変化などに伴って、家族の在り方、働き方、暮らし方が大きく変化しており、今後は、「地域共生社会」の実現が地域福祉の大きなテーマになると認識しております。地域共生社会とは、これまでの縦割りの「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる社会を指します。そうした社会では、誰もが役割を持ち、ある日は誰かに支えられ、ある日は誰かを支える、そのような関係性が生まれ、市民一人一人の暮らしと生きがい、地域がつくられていきます。
重層的支援体制整備事業は、このような地域共生社会を実現するための一つの手法であり、属性を問わない居場所づくりに係る受皿の確保や、相談に係る関係者の役割分担及び支援の方向性を示す多機関協働事業の構築といった課題を踏まえた上で、現在、導入に向けて検討を進めているところでございます。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
導入に向けた検討をしていただいているとのことで、何とぞよろしくお願いいたします。
それぞれの自治体の課題は千差万別です。高齢化、過疎化が進んでいる市町と、人口流入が続いている比較的高齢化率の低い市町とでは、解決しなければならない課題は大きく違ってきます。そのような課題の違いがあまり考慮されない全国一律の補助金事業や典型的な困り事に対して、それぞれに対応していくこれまでのやり方では、今後立ち行かなくなることが予測されます。補助金制度を緩和して各市町の裁量を増やして、それぞれの創意工夫を促していく。中央で制度改正を行っていくのではなく、各市町の中で制度の改善サイクルを回して、自分たちのまちの課題は自分たちで解決していくといったようなことが求められているのかなと感じています。
このような流れは今に始まったのではなく、介護予防・日常生活自立支援総合事業においても、各市町の創意工夫を強く求められました。本市でも、本市の実情に応じた介護予防施策を検討、実施してこられたと思います。今後も様々な分野において、地域へ権限を移譲し、地域の創意工夫を促していく、自立した地方自治体をつくっていく、このような流れにあると思います。本市でも、ぜひ重層的支援体制整備事業に手を挙げていただいて、本市の実情に応じた地域共生社会を市民の皆様とともにつくっていきたいと思っております。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。