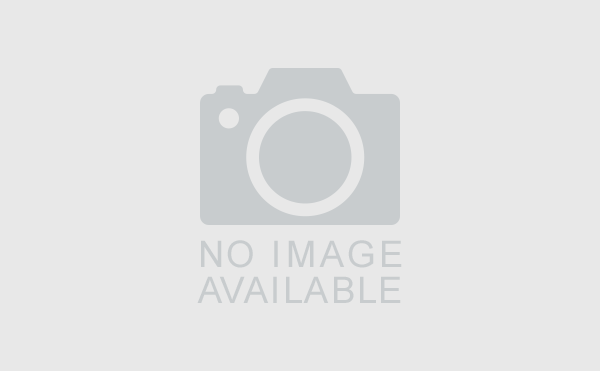令和5年12月定例会質問通告
1 要介護者・障がい者(児)の参加に向けた本市の取組について
仏教において人は生・老・病・死の四苦は人間の基本的な苦しみだと言われている。つまり、人間である以上は病や老いにより介護や支援が必要になる、あるいは生来その状態であることは避けられない事象である。住み続けたいまちを目指す本市にとって、介護や支援が必要な方々にも、住み続けたいと思っていただくように努力することは異論のないところであると考える。
リハビリテーションは活動と参加に焦点を当てて行うべきものだとされているが、介護や支援を必要とされる方々の参加はいまだ様々な状況において障壁があるものとなっている。そこで、本市のイベント、普段の居場所や臨時の宿泊場所などについての本市の取組について伺う。
- ⑴ 要介護者・障がい者(児)の本市イベント参加における配慮について
- ア 市民祭における車椅子を利用される方々の乗降スペースについて
- イ 今後のイベントにおける取組について
- ⑵ ごちゃまぜ(インクルーシブ)なまちへの入口としての基準該当サービス及び共生型サービスについて
- ア 現状について
- イ 今後の方針と展望について
2 不祥事の発見統制について〜不祥事を小さな芽のうちに摘むために〜
一定程度の組織において、不祥事は「あってはならないもの」と遠ざけるのではなく、「必ず起きるもの」として正面から向き合う必要がある。実際に本市では公金詐取事件という大きな不祥事が発生した。令和5年6月定例会において、性弱説に基づいた業務システムの構築が必要であるとの前提に基づいて質問を行った。これは「予防統制」の観点によるものであった。一般に平時のリスク管理では、不祥事を発生させないための「予防統制」に力点が置かれてきたが、最近では一定の確率で不祥事が発生してしまうことを前提とした「発見統制」に力点が移りつつある。そこで不祥事にどのように対処しているか、「発見統制」の観点から本市の現状について伺う。
- ⑴ リスク情報を収集し、適切に報告するための研修について
- ア 中間管理層への研修の実施状況について
- イ 研修内容について
- ⑵ ヒヤリ・ハット報告について
- ア 各部・課への依頼方法について
- イ ヒヤリ・ハット報告の現状について
- ⑶ 公益通報制度の浸透度と利用状況について
- ⑷ 苦情の対応記録について
3 身近に頼れる方のいない、一人暮らしの高齢者あるいは老老介護世帯への本市の対応について
総務省関東管区行政評価局が令和4年3月29日に公表した高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)−入院、入所の支援事例を中心として−によると、一人暮らしの高齢者は全国で約737万人おり、入院や施設入所の際に、身元保証人が立てられない高齢者も増加の見込みと報告されている。また、「自治体が直面する高齢者身元保証問題の突破口(沢村香苗 著)」によると、現在の高齢単身世帯は配偶者と死別した人の割合が高く、離れて住む子世代がいることも多いが、今後は未婚の人の割合が大幅に増えると推計されている。また、家族の疎遠化も進んでおり、今後身近に頼れる方のいない単身の方が増えていくことも危惧されている。そこで、今後増えていくであろう、高齢者の身元保証問題について、現状と今後の方針についてお伺いする。
- ⑴ 身近に頼れる方のいない、一人暮らし高齢者あるいは老老介護の世帯数について
- ⑵ 救急車への同乗を求める基準について
- ⑶ 入院や入所における身元保証の現状について
- ⑷ 高齢者身元保証問題への本市の考え方について
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。