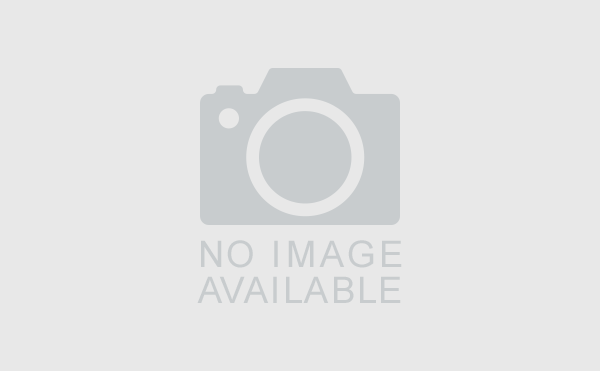要介護者・障がい者(児)の参加に向けた本市の取組について
◆1番(勝股修二) ただいま議長よりお許しがありましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
ちょっといろいろどきどきすることがあってちょっと落ち着いていないんですけれども、本当通算3回目の質問になります。まだまだお見苦しいところがあると思いますが、何とぞお許しいただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、質問事項1、要介護者・障がい者(児)の参加に向けた本市の取組についてお尋ねしていきます。
仏教において、人は生・老・病・死の四苦は人間の基本的な苦しみだと言われています。人間である以上は病や老いにより介護や支援が必要になる可能性があることは自然の摂理です。住み続けたいまちを目指す本市にとって、介護や支援が必要な方々にも、住み続けたいと思っていただくように努力することは異論のないところであると思います。
私の専門分野であるリハビリテーションは、活動と参加に焦点を当てて行うべきものだとされています。リハビリというと、筋トレとか電気を当てたりといったイメージを持っておられる方が多いんですが、本来の意味は、再びその方にふさわしい状態になることを意味しております。宗教上の名誉回復、政治家の政界復帰や麻薬中毒患者の社会復帰など、リハビリテーションという言葉は様々な場面において使われています。つまり、人生の質--以下QOLとします--を高めるために活動と参加に焦点を当てていこうということです。
一時期ピンピンコロリという言葉がはやっていました。これは突然死により介護される期間がなくなってほしいという、何ともいいのか悪いのかちょっと判断がつきかねる考え方なんですが、突然死の割合は大体10から20%程度で、ほとんどの方は介護が必要な状態を経過していきます。当時は健康寿命を延ばすことで、社会保障費の抑制につながらないかということでのピンピンコロリでしたが、健康寿命が延びれば平均寿命も延びるということで、社会保障費の抑制にはつながらないということが分かって、現在では、健康寿命の延伸についてはQOLの向上に向けての取組となっております。
本市は、寝たきりにさせないまちづくり、外に出かけたくなるまちづくり、住み続けたくなるまちづくりを3つの目標に掲げております。このうち、寝たきりにさせないまちづくりについては、心身機能、身体構造、活動が寝たきりという状態になることをどのように防ぐかといった意味合いであるということでした。実際にこの目標による施策は筋トレやウオーキングなどによる体力づくりなどとなっております。
しかし、寝たきりにさせないまちづくりにはもう一つの意味があると私は考えます。心身機能、身体構造、活動が寝たきりの状態になったとしても、参加において寝たきりという状況にさせない、不自由な体の状態でも何とかして社会参加につなげていき、出かけたくなるようにするという考え方も必要ではないでしょうか。
そこで、介護や支援を必要とされる方々のQOLを高めるための参加について、本市の考え方と取組についてお伺いしていきます。
⑴ 要介護者・障がい者(児)の本市イベント参加における配慮について
ア 市民祭における車椅子を利用される方々の乗降スペースについて
◆1番(勝股修二) 小項目(1)、要介護者・障がい者(児)の本市イベント参加における配慮についてに入ります。
本年10月初めに開催された市民祭において、車椅子を使用されている方の中に車の乗降に非常に困った方がいたとお聞きしましたが、現状においての市民祭における車椅子を利用される方々の乗降スペースについてお伺いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
今年度の市民祭では、車椅子を利用される方などの駐車スペースを長池下駐車場に用意しておりましたが、乗降専用のスペースについては用意しておりませんでした。
乗降専用のスペースについては、車椅子を利用される方の利便性が向上し安全の確保もしやすいと思われますので、今後もより多くの方にお越しいただき、楽しんでいただける市民祭となるよう、乗降専用のスペースも含め総合的に検討していきたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 総合的に検討していただけるとのことで、ありがとうございます。
今回は車椅子のリフトを使用した乗降において、少し危険を感じながら行っていたということでした。市民祭は参加人数も多く非常に混雑する上に、城山公園周辺は道も狭く高低差もあるために、なかなか難しいことも理解いたしますが、次回については確実な改善をお願いいたします。
イ 今後のイベントにおける取組について
◆1番(勝股修二) 本市には市民祭以外にも様々なイベントがあります。市民祭やさくらまつりは産業課、夏フェスタは市民活動課、あさひ冬フェスタ、今週末ですかね、9日ですね、は都市計画課など、様々な部署がそれぞれ担当して運営していただいていますが、車椅子を利用される方々の対応はやはり健康福祉部局がノウハウを持っていると考えます。
そこで、今後、本市イベントにおける配慮について連携して当たり、また、方針やガイドラインをあらかじめ示しておくことなどはできないでしょうか。
イ、今後のイベントにおける取組についてお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
市民の皆さんに等しく行政サービスを提供する基本は、ユニバーサルデザインの考え方であると認識しております。
このため、市が主催するイベントにおいても、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが参加しやすくするための配慮が必要だと考えております。
具体的には、企画の段階から、利用しやすい会場の選定、分かりやすい情報の発信、安全・安心なアクセス、会場運営のハード・ソフト両面の配慮など、様々な事柄を念頭に置いて、準備を進めていくことが重要であると考えております。
現時点では、イベント開催などに係るガイドライン等を作成する考えは持ち合わせておりませんが、冒頭、申し上げたユニバーサルデザインについては、官民連携による参考取組もあるようですので、そうした情報については、他の部署とも共有したいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
イベントの企画というのは本当に大変で、ユニバーサルデザインの理念を企画段階で取り込んでいくことは実は結構大変なことだと承知しております。また、高齢者福祉、障がい者福祉に携わったことのない職員にとってはより一層です。情報の共有にとどまることなく、各イベントの企画段階から健康福祉部局の方がその視点を持って関わっていただきますよう、要望として申し伝えます。よろしくお願いします。
次に入ります。
⑵ ごちゃまぜ(インクルーシブ)なまちへの入口としての基準該当サービス及び共生型サービスについて
ア 現状について
◆1番(勝股修二) 小項目(2)、ごちゃまぜ(インクルーシブ)なまちへの入口としての基準該当サービス及び共生型サービスについてに移ります。
本年度末にて尾張旭市障害者デイサービス事業が、市としての役割を終えたということで、終了することになりました。確かに、市内の障がい者向けの施設は以前と比べると増えてきており喜ばしいと考えますが、聞くところによると、本デイサービス事業を利用されていた方々の移行先は、ほかの市町を頼らざるを得ないということです。近隣市町と連携して支えていくことはとてもよいことだと考えますが、市内に一定の受皿を用意しておくことも必要なことであると考えます。また、相談員さんたちの感覚でも受入先はまだまだ不足しているということでした。
障がい福祉は高齢者福祉と比較して、なかなか整備が進まないのが現状です。平成18年に障害者自立支援法が施行されたときには、身体、知的、精神と障がいの種別を問わないサービスの一元化や実施主体を市町村に一元化、ほかに批判は多くありましたが、1割の定率負担、障がい程度区分など、介護保険との統合を見越した制度設計なのかなと感じておりましたが、なかなかそのようにはなっておりません。
しかし、富山県では、高齢者も子供も障がい者も一緒と、年齢や障がいの有無にかかわらず誰もが一緒に身近な地域でデイサービスを受けられる富山型デイサービスというのが、介護保険施行前より運営されていました。この取組を国も認めて特区制度などにより推進されて、徐々に全国にも広がりつつあります。富山県では、富山型デイサービスのような高齢者、障がい者、子供が共に利用でき、身近な地域で必要な福祉・コミュニティーのための機能をコンパクトに1つの場所で担う施設を共生型福祉施設と定義して、毎年度、各都道府県に対して調査を実施し、その数を集計していますが、平成15年度には全国で205か所だった共生型福祉施設が、平成29年度時点では2,138か所と、15年足らずで約10倍に増加しております。その共生型福祉施設を運営していくための制度的な枠組みが基準該当サービスや共生型サービスとなりますが、本市にはこれらのようなサービスを提供している事業所はありますでしょうか。
小項目(2)のア、現状についてお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
基準該当サービスとは、介護保険や障がい福祉のサービスにおいて、県の指定基準は満たしていないが、市が定めた基準を満たす場合に、サービスの提供が可能となるものです。
一方、共生型サービスは、基準該当サービスを発展させた形で、介護または障がいのいずれかの指定を受けている事業所が、県の指定基準を満たしていなくても、指定を受けていないほうのサービス提供が可能となるものです。
本市では、基準該当サービスは行っておりませんが、障がい福祉サービスを共生型で指定を受ける形で、共生型サービスを行っている訪問介護事業所が1か所ございます。
なお、共生型の指定は受けておりませんが、介護と障がいの両方の指定を受けている訪問系の事業所は14か所ございます。
以上です。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
現状では、地域資源が高齢と障がいに分かれてしまっている。特に通所や宿泊のサービスについてはごちゃまぜでは対応できないことが分かりました。
イ 今後の方針と展望について
◆1番(勝股修二) 障がい者福祉において現在問題となっているのが、親亡き後の問題ですが、そうなる前に親の高齢化、要介護化の問題もあります。世話をしてきた親に介護が必要になった場合に、制度の問題で引き離されてしまう。親は介護保険の施設に、子は障がいの施設にということもあったりするわけです。また、障がい者が65歳になった途端に、それまで通い慣れていた通所施設から介護保険の通所施設に変わらねばならないといった問題もあります。共生型の施設であれば、それらの問題を幾らかは解決できる可能性もあります。それらの施設の開設や既存施設の移行などを市として音頭を取って推進をしていただく、あるいはサポートしていくなどすることはできないでしょうか。
イ、今後の方針と展望についてお伺いいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
国の障がい施策推進に伴い、本市内にも多種多様な障害福祉サービス事業所が開設されてきましたが、重度障がい者の受入先の不足については、課題の一つであると認識しております。
基準該当サービスや共生型サービスは、そうした課題を解決する一つの手法として考えられます。これらの制度を推進することにより、事業所の選択肢が広がる、障がい者が65歳を過ぎても使い慣れた事業所を継続利用できる、多世代共生ができるなどのメリットが生じますが、現在は、まだあまり普及していないのが実情です。
その要因としましては、通常より報酬が低いため採算が取れない、高齢者と障がい者が同じ事業所を利用するため、新たな設備投資や支援員の質の向上が必要になる、また、制度の必要性に係る理解の不足なども挙げられます。
いずれにしましても、今後、共生型サービスなどを推し進めていくためには、事業者の皆さんの協力が不可欠でありますので、意見聴取など事業者との対話を重ねていく中で、方向性を見いだしてまいりたい、そのように考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
実際問題、高齢者の現場の方が障がい者の方を受け入れるのをためらう、あるいはその逆のようなことも確かにあります。
しかし、介護保険が始まった当時は、現場の方々の間で、入居施設でみとりをするなんてとんでもないという御意見もありましたが、現在では、施設みとりは当たり前のように行われております。報酬については、低いことを市として認識しておられるのであれば、施策の推進に向けて何らかの助成をするなど、ぜひ御一考をお願いいたします。
知らないこと、未経験のことを始めるときは、現場の方や経営者の方など誰でも怖いものです。ですので、ごちゃまぜな施設を始めてしまえば何ということもなかったということになり、尾張旭市民の福祉が一層増進することを祈って、本質問事項を終了させていただきます。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。