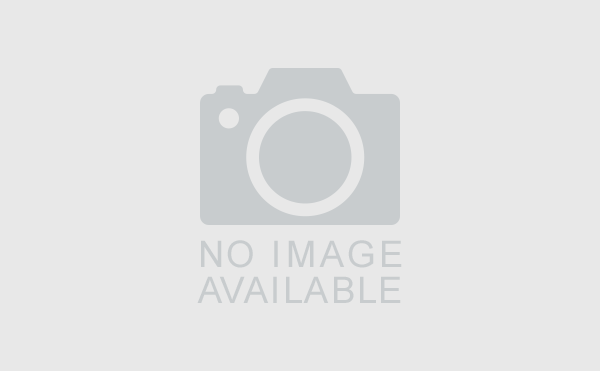身近に頼れる方のいない、一人暮らしの高齢者あるいは老老介護世帯への本市の対応について
⑴ 身近に頼れる方のいない、一人暮らし高齢者あるいは老老介護の世帯数について
◆1番(勝股修二) 次に、質問事項3、身近に頼れる方のいない、一人暮らしの高齢者あるいは老老介護世帯への本市の対応についてに入っていきます。
総務省関東管区行政評価局が令和4年3月29日に公表した高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)、サブタイトルが「入院、入所の支援事例を中心として」によると、一人暮らしの高齢者は全国で約737万人おり、入院や施設入所の際に、身元保証人が立てられない高齢者も増加の見込みと報告されています。
また、成書「自治体が直面する高齢者身元保証問題の突破口」、こちらの本になりますけれども、これが「現在の高齢単身世帯は配偶者と死別した人の割合が高く、離れて住む子世代がいることも多いが、今後は未婚の人の割合が大幅に増える」と推計されています。それだけ家族が薄くなっていってしまうということですね。
また、家族の疎遠化も進んでおり、今後、身近に頼れる方のいない単身の方が増えていくことも危倶されているということです。
確かに介護の現場においても、身近に頼れる方のいない高齢者の割合が増えてきている印象です。また、私はケアマネジャーの法定研修にて講師をさせていただいているんですが、その研修では、各自の事例を持ち寄って勉強をさせていただきます。そこでは最近身寄りのない方や身元保証人を必要とする方についての事例が増えてきています。そこでは持ち寄る事例は困っている事例を持ってくる場合が多いですので、それだけ現場では対応に苦慮しているということだと思います。
そこで、今後増えていくであろう高齢者の身元保証問題について、現状と今後の方針についてお伺いしていきます。
まずは、現状の把握から行ってまいります。
小項目(1)、身近に頼れる方のいない、一人暮らし高齢者あるいは老老介護の世帯数について、本市の現状についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
本市では、毎年、高齢者の状況を把握し、緊急時の対応などに役立てることを目的として、民生委員の方々に一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を訪問していただく高齢者世帯等実態調査を行っております。令和4年度の調査結果によりますと、一人暮らし高齢者数は2,615人、高齢者世帯数は2,803世帯でありました。
なお、老老介護の世帯数については把握しておりませんが、当該実態調査によって、何らかの支援が必要と思われる方について民生委員から報告を受けた場合は、地域包括支援センターなどにつなげているところです。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
今回ちょっと事前の打合せで数をお聞きしたときに、こちらの一人暮らし世帯と高齢者世帯について、ちょっと昔のデータを頂きました。過去にも何度かこの数については、この質問にて答弁をされていることだと思うんですけれども、その推移についてどうなっているかなということで、ちょっとグラフにしてみました。
現状、こんな状況です。大体10年前に比べて倍増をしております。さらにちょっとこの角度を見ていただくと、だんだんと加速しているようにも見えますね。なので、10年後というか2050年までは高齢者増え続けるということになっておりますし、家族の希薄化というのもどんどん進んでいますので、これがもっともっと突き抜けていってしまう可能性もあるんじゃないかと、少々危惧をしております。
⑵ 救急車への同乗を求める基準について
◆1番(勝股修二) では、今の数を見た上で、小項目(2)のほうに移っていきます。
一人暮らしの方が急病などで倒れられた場合において、訪問介護のヘルパーさんやお迎えに来るデイサービスなどの職員さんなどが発見して、救急要請することなどもあるかと思いますが、そのような場合に同乗を要請される場合があるようです。ヘルパーさんやデイの職員さんが同行しても、身元の保証や医療同意などができるわけでもありませんし、緊急連絡先情報を得たい場合は、ケアマネジャーなどに問い合わせるほうが確実です。
また、医療の方針を確認したい場合でも、御本人の意向やエンディングノートの保存場所を知っている可能性があるのは、やっぱりケアマジャーなどです。
同乗していただくメリットもそんなに多くないと考えられますが、逆に同乗した場合は、訪問介護やデイサービスにおけるほかの利用者さんの対応がおろそかになってしまいます。
そこで、救急搬送時における救急車への同乗を求める基準についてお伺いします。
◎消防長(各務誠司) お答えします。
救急隊が関係者に救急車への同乗を求める基準につきましては、尾張旭市救急業務規程の中に「未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者に同乗を求めるものとする」と規定されております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 御答弁ありがとうございます。
原則とのことでしたので、ぜひ今後の運用方針について御検討をお願いしたいと思いますし、打合せの段階では大分いろいろ考えていただいているということをお聞きしておりますので、大丈夫だと思いますが、介護の現場にはちょっと優しい方が多くて、そのような緊急の状況において、同乗を要請されたらちょっとやっぱり非常に断りづらいですし、断るのにも大きなストレスがかかります。本当に緊急の場合でごちゃごちゃしちゃっている状況で、ぱっと乗ってくださいと言われたとしても、結構言われたほうはかなりちょっとストレスになってしまうというところもありますので。
また、人手不足の中で、効率的に人手を運用していくことは非常に重要です。数日前に、介護現場、働き始める人を離職が初めて上回るということで、担い手不足が危機的であるというニュースが出ていました。今後、人手不足が深刻化していく中で、介護従事者の労働環境の改善は当然ですが、いかに少ない人数で回していくかということも重要な視点となっていきます。
今後増えていくと予測されている一人暮らし高齢者について、介護、救急、医療・病院等が連携をして、事前に救急搬送時の対応や情報をどのように得ていくのか、伝達していくのかということを一定の方針を共有できればよいのではないかと考えますので、ぜひその中で介護、救急医療等でコミュニケーションを取って、対応方法について事前に決めておいていただけると非常にありがたいと思います。よろしくお願いします。
次の小項目に移ります。
⑶ 入院や入所における身元保証の現状について
◆1番(勝股修二) 本市のホームページにおいても、身寄りがない人の入院及び医療に意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインや身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについてなどの文書が掲載されており、身元保証問題への対応をもう既にされているかと思います。しかし、伝え聞くところによりますと、近隣の医療機関などにおいて、ケアマネジャーなどが入院承諾書などに署名を求められるなど、現場の運用が整理されていないことも聞き及んでおります。
また、本質問事項の冒頭において紹介した調査結果によると、約6割の病院・施設が「身元保証等が必要になる場面ごとに個別に対応する」と回答しておりますが、病院では約6%、施設では約20%が「入院・入所をお断りする」と回答されております。身元保証人の不在は、費用の回収が困難となったり--入院費等ですね--退院・退所ができなくてベッドが空けられなくなったりなど、病院・施設経営の悪化をもたらす原因にもなって、現行の制度下では病院・施設は身元保証人を求めざるを得ないということも致し方のないことであることも分かります。
そこで、小項目(3)、入院や入所における身元保証の現状について、本市において何らかの問題を生じた事例を把握されているかをお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
高齢者の総合相談業務を担っている担当者に確認したところ、要介護者などから、身元保証人がいないことを理由とした入院や入所の拒否に関する相談を受けたことはないとのことでした。このことは、平成30年に厚生労働省から発出された通知に基づいているからだと考えております。
以下、該当部分を読み上げます。
「介護保険施設に関する法令上は、身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」と示されております。
答弁は以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
厚労省の通知はありますが、これは身元保証を求めてはいけないという禁止規定ではなく、また、病院や施設の経営上の負担を考慮したものでもありません。現状は病院や施設、相談業務に従事されている現場の方々の御尽力により、成年後見制度や身元保証等高齢者サポートサービスなどを活用して、何とか回っている状況なのかとも思います。
しかし、今後このような問題が増えていく状況において、どのように備えておくか考えておくことも必要です。
次の小項目に移ります。
⑷ 高齢者身元保証問題への本市の考え方について
◆1番(勝股修二) 小項目(3)はいわゆる狭い意味での身元保証問題をお伺いしましたが、ここからはライフスタイルの多様化により、家族、地域や慣習にとらわれることなく人生の選択肢を選び取り、個としての幸福の追求を是とする現代社会においての問題として、広義の身元保証問題についてお尋ねをしていきます。
身元保証問題の本質は、これまで家族や親族による無限・無償の支援が期待できなくなってきたことにあります。その支援において、法律行為や手続の支援、また財産管理などについては、現状でも成年後見制度というものがありますが、制度上の制約が多いことから、その隙間を埋める形で、身元保証等高齢者サポート事業というのが年々増えてきています。
身元保証等高齢者サポート事業というのは、家族や親族に身元保証人を依頼できない人、または依頼したくない人、どうしても親子間の関係が悪くて子供に頼りたくないという方も、最近はすごく増えてきています。そういう方々に対して、身元保証人になってくれる人がいないという狭義の身元保証問題と、老後の面倒を見る人がいないという広義の身元保証問題の双方を解決するためのものであることが多いですが、今後の需要増加が見込まれる事業であり、その健全な育成が望まれています。
しかし、この事業には規制する法令もなく、また、監督官庁もないことから、非常に危うい面も持っています。
このような状況の中、本日、朝一の質問でもありますけれども、横須賀市ではエンディングプランサポート事業、終活情報登録伝達事業、また、千葉市では終活提携協定、福岡市ではずーっとあんしん安らか事業など、複数の自治体でこの問題への取組が始まってきています。また、近くの半田市さん、また新潟県の魚沼市では、この問題に対応するガイドラインも作成されています。
本市でも先ほどお伝えしたように、ホームページに厚生労働省が作成をしたガイドラインというのを掲載はされてはいるんですが、このガイドラインは実はあればいいという類いのものではなくて、地域においてその作成段階から様々な関係する方々が関わることによって、地域資源の洗い出しや意識の醸成、役割分担がなされていくということです。ですので、ガイドラインをつくっている間に様々な方が仲間になっていって、地域で活躍するプレイヤーになっていってくれるということですね。
そこで、個人を取り巻く層が希薄化する中で、本市市民の高齢期の生と死の尊厳を保つために、本市はどのように対応し、また、対応していくのか。
小項目(4)、高齢者身元保証問題への本市の考え方についてお伺いをいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
家族の形が変容する中、家族に代わって行う高齢者身元保証サービスの需要は今後ますます高まっていくものと考えておりますが、議員が先ほどおっしゃったとおり、こうしたサービスを提供する事業を規制したり監督する省庁や法律がない点は、私どもも大変危倶しております。
本市におきましては、身寄りのない高齢者が安心して医療や介護を受けられる環境を整えるためにも、エンディングノートや終活に関する講演会などを参考にして、元気なうちに自ら備えていただくよう、周知啓発に努めているところです。
そして、同時に国や他の自治体の対応状況を踏まえ、市の関与の必要性について研究したいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。もう本当にぜひ研究をお願いいたします。
身元保証等高齢者サポート事業については、先ほど申し上げた私がいろいろやっているケアマネの研修においても、本当に金銭的な面でかなり危うい話もちょくちょく出てきています。本当に質問事項2で出したように、現場においてリスク情報が捉えられている状態でも、監督官庁や法令がないためにレポートラインがそもそもなくて、対応ができない状況でもあるんです。
本事業は今後ますます重要になっていくというのは先ほどお伝えしたんですが、何としてもやっぱり健全に育成をしていかなくてはなりません。法令がないのであれば、市としてまた条例や規則による対応も一考していく必要がありますし、私としても国に対して何とか意見書をつくっていくとか、そのような対応をしなければならないと、今、非常に危機感を覚えているところです。
現段階において、高齢者身元保証問題に対して確かな解を持っている方はいません。本質問を立てるに当たって、果たしてどこまでが市の一般事務なのか非常に悩みましたし、私自身明確なビジョンがない中、質問させていただくのは非常に心苦しいものでした。しかし、既に顕在化しつつある問題であり、また、今後増えることが確実視をされている社会課題です。尾張旭市民の福祉を増進するために地方自治体としてできること、また、しなければならないということを検討していくことは、必須の分野であると考えております。
今回、紹介させていただいたほかの市町の取組にあるように、情報を把握して他機関のコーディネートをしていくことも必要になるかもしれません。自助、互助を基本としている以上、インフォーマルなサポートを発掘していくことも必要です。自治体は個人の友人関係に立ち入ることはできないんですけれども、身元保証問題の意識喚起を図るときに、隣近所の住民同士の協力の仕方をそこで提案していったりとか、住民がよく利用する地域のお店を接点として、活用したりすることを提案していったりとか、そういったことを検討する価値があるのではないでしょうか。
この問題については、地域の現場において御尽力いただいている皆様も、やっぱり危機感を持って向き合っておられます。本市においても10年くらい前からですかね、旭丘学区のほうから始まったということをちょっとちらっとお聞きしたんですが、緊急時情報カード、マグネットシートが配布されていて、現在ではホームページに掲載されていて、それを印刷して活用してくださいということになっておりますが、こちら地域の民生委員さんや児童委員さん、また校区社協さん、また自治会の皆さんが地道にこのカードの普及啓発を進めていただいております。
多くの様々なプレイヤーに参加していただかないことには、この問題は解決に向かっていきません。ぜひ市としても、広義の身元保証問題に関して積極的に地域の皆様の声を聞き取っていただき、取組をサポートしていただきますようお願い申し上げます。
また、私自身も本問題の解決に全力で立ち向かうことを心に決め、私の質問を締めさせていただきます。今回も本当に多くの皆様に御協力いただき、感謝申し上げます。ありがとうございました。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。