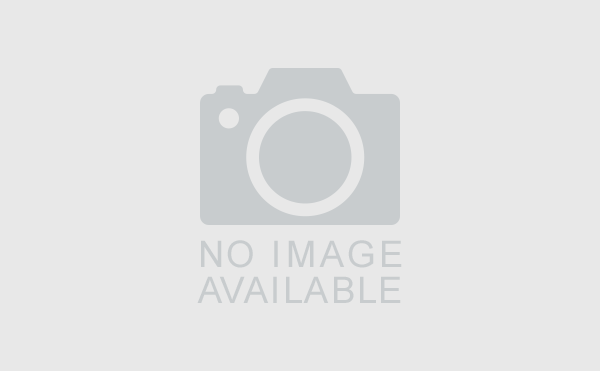令和6年3月定例会質問通告
1 障がい者と呼称される方の就労支援について
障がい者と呼称される方、特に知的障がいで療育手帳をお持ちの方、精神障がいで精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が増加傾向にある中、障がい者の就労支援は大きな問題となっている。障がい者の雇用促進においても、障害者雇用率が段階的に引き上げられている最中であり、本年4月からは、国及び地方公共団体にあっては2.8%、都道府県等の教育委員会にあっては2.7%、一般事業主にあっては2.5%、一定の特殊法人にあっては2.8%と定められている。また、第7期障がい者計画に向けた障がいのある人等へのアンケート調査においては、雇用・就労については優先度が高く、満足度が低い課題として顕になっている。
本市第6次総合計画にも位置付けられる予定の、障がい者の自立と社会参加の促進に向けた施策の詳細について伺う。
- ⑴ 本市行政機関における障がい者雇用について
- ア 雇用率について
- イ 就労支援に向けた取組について
- ⑵ 本市の障がい者雇用について
- ア 市内企業における障がい者雇用率について
- イ 本市市民(手帳所持者)の就労状況について
- ⑶ 企業、行政、就労支援事業所等の連携体制の構築について
- ⑷ 就労支援関連事業者に対する支援について
- ア 周知啓発について
- イ 働き手の育成について
- ウ バザー(福祉市場)等の開催について
- エ 優先調達の推進と受注機会の拡大について
2 自治会とその入口としての市民活動について
自治会加入率の改善に対して、様々な検討がなされているが、残念ながら加入率は年々低下傾向である。自治会などの地域活動は、防災やごみの収集、親睦など、非常に重要な機能を持っているが、その重要性の認識についてはなかなか広まらないのが現状である。しかし、自治会制度は地縁や血縁などにより、すでに関係性の深いコミュニティで生まれ、家族の中で働き手が一人いれば家族を養っていくことができる時代にその変遷を辿ってきた制度であり、時代に合わなくなっているのも実情である。
内閣府による調査では、社会活動への参加に対する国民の意識は、社会の人間関係の希薄化がいわれる中にあっても、6割以上の国民(63.4%)が社会貢献の意識を持っており、その意識を行動につなげるきっかけづくりが必要とされている。
そこで、比較的若い世代の自発的な市民活動を支援することで、自治体加入の入り口となる可能性を模索するべく、本市の現状と考え方について伺う。
- ⑴ 自治会の現状について
- ア 加入率について
- イ 目標値とその考え方について
- ウ 自治会における業務負担の軽減について
- エ 自治会・町内会活動に関する調査結果の受け止めについて
- ⑵ 自治会やPTAへの参加における地方自治体の地域貢献活動休暇について
- ⑶ 文化会館における市民活動において、営利と判断される基準について
- ⑷ 経済的に自立した市民活動団体となるための具体的な方法について
- ⑸ 市民活動団体と自治会の連携について
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。