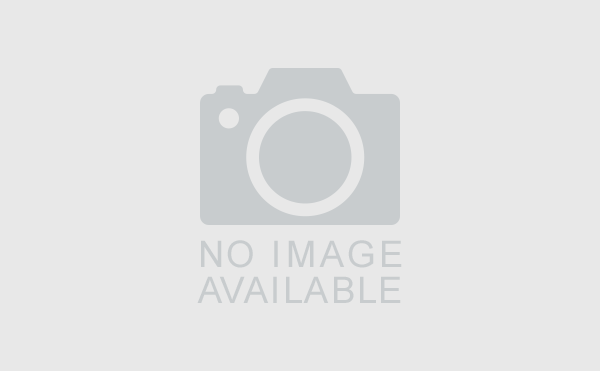障がい者と呼称される方の就労支援について
◆1番(勝股修二) ただいま議長よりお許しがありましたので、通告に従い、順次質問させていただきます。愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
市長には、施政方針演説において、「幸せつむぐ 笑顔あふれる 尾張旭」について説明をしていただきました。まさに、地域共生社会を体現した言葉であると感動いたしました。今回の私の質問は、地域共生社会をどう具体化していくかというところにありますので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。
今回も質問項目が多くて、かなり駆け足になってしまいますことを、事前におわび申し上げておきます。
⑴ 本市行政機関における障がい者雇用について
ア 雇用率について
◆1番(勝股修二) それでは、質問事項1、障がい者と呼称される方の就労支援についてお尋ねしていきます。
この質問を組み立てるに当たって、就労支援の対象者の方が多く診断されている発達障がいについて調べ直してみると、特にASD、Autism Spectrum Disorder、自閉スペクトラム症の特性は、私自身の幼少期を思い出すようなことばかりで、私自身ASDの範疇に入っていたのだなと思いました。実際に本を読み始めると、何時間でも時間を忘れて読みふけってしまうとか、学校では毎日忘れ物をしてしまうとか、思考が飛び気味で、私が発言すると、みんなが黙り込んでしまうようなこともあったということが思い起こされています。
ここで、医療や福祉の現場において、非常に大事な考え方であるICF、国際生活機能分類というのを、少し紹介をさせていただきますが、御存じの方もいらっしゃると思いますけれども、この分類は、福祉政策を考えていくためには非常に重要な考え方ですので、行政に携わる方全てに覚えていただきたいと思っております。
生活機能には3つの要素があると分類をされており、ちょっと小さくて申し訳ないですけれども、1つ目は心身機能、身体構造です。2つ目に活動、3つ目に参加となります。これらの生活機能に対して、疾病やけが、ストレスなどが、一番上のところ、健康状態として定義をされます。また、その方を取り巻く物的環境、人的環境、社会的環境を環境因子と定義して、その方自身の年齢や性別、価値観や内面の思いなどは、個人因子と定義されます。これらの7つの要素がそれぞれに影響をし合って、その方の生活機能を形づくっているという考え方になります。
非常にざっくりとした説明で申し訳ないんですけれども、何を言いたいのかというと、障がい者というのは、その時代、社会環境によってつくり出されるものであるということです。
私の経験上の話で申し訳ありませんが、訪問リハビリテーションの高齢の利用者さんの中に、若い頃からほとんど誰とも話すことがなかったような方や、何か気に入らないことがあれば、すぐに暴力に訴えてきた方などが、ちらほらといらっしゃいました。今であれば、社会不適合者の烙印を押されてしまうような方々なんですが、それでも、その時代においては珍しいものではなくて、家を持って、家族をつくってこられました。仕事をするに当たって、コミュニケーション能力というのはそれほど必要ではなくて、手を動かしていれば、それなりの収入を得られた時代だったからです。
逆に、寡黙な信頼の置ける職人として、重宝をされてきたほどでした。また、現在では、過集中とされている、寝食を忘れて一つのことに没頭することは、すばらしいことだと考えられていました。
しかし、現代ではそういうわけにはいきません。産業用ロボットが発達し、手作業のみの仕事がほとんどなくなってしまいました。また、仕事の合間で、他のことに対応できないようであれば、ビジネスマンとして失格と言われてしまいます。
このような現在の労働環境では、コミュニケーション能力と複数のことを同時にこなすマルチタスク能力が重要視をされて、それらが苦手な方々は疎んじられて、理不尽な待遇を受けて、さらには職場から追いやられてしまうようなこともあり、そうして、二次障害である精神疾患や強度行動障害などを病んでしまうような状況にあります。
このような中、障がい者と呼称される方が本市でも増加傾向にある中、障がい者の就労支援は大きな問題となっています。障がい者の雇用促進においても、障がい者雇用率が段階的に引き上げられているさなかであり、本年4月からは、国及び地方公共団体にあっては2.8%、一般事業主にあっては2.5%となりました。
また、本市の第7期障がい者計画案においては、就労に関する問題が、優先度が高く、満足度が低い課題としてあらわになっています。
そこで、障がい者の自立と社会参加の促進に向けた施策の詳細について伺っていきます。
小項目(1)、本市行政機関における障がい者雇用について、こちらは令和元年6月定例会において、質問がなされておりますが、来年度の法定雇用率変更に当たって、再度確認させていただこうと思います。
ア、雇用率についてお伺いします。
◎企画部長(松原芳宣) お答えします。
本市の障がい者雇用率は、令和5年6月1日現在で、市長部局が2.72%、教育委員会が3.77%であり、法定雇用率を上回っております。
また、新たな雇用の促進に取り組んでおり、令和6年度においても、法定雇用率を上回る予定でございます。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
教育委員会については3.77%ということで、かなり上回っているというところですし、市長部局においては、現状では、法定雇用率を上回っており、また、来年度も見通しが立っているということです。今後も新たな雇用の促進に取り組んでいただき、法令を遵守していただきますようお願いいたします。
障がい者の就労支援については、行政が先頭に立って共生社会を目指していかなければなりません。その意味からも、市役所等において、障がい者の就労体験やインターンの機会を積極的に提供をしていくべきであると考えます。
イ 就労支援に向けた取組について
◆1番(勝股修二) そこで、イ、就労支援に向けた取組についてお伺いします。
◎企画部長(松原芳宣) お答えします。
本市では、学生を対象にインターンシップ実習を実施しており、ホームページにおいて、年間の実習実施計画表や申込書などを公表しています。学生は、計画表に記載のある実習可能期間や実習内容を参考に、希望する担当部署を決定して申し込みます。
実習の内容としては、庶務的な事務やイベントの運営など、多種多様な業務がございます。
対象者について、障がいの有無は不問としておりますので、障がいのある学生が申込みいただくこともできます。
また、障がい者の就労支援に向けた取組として、瀬戸つばき特別支援学校の生徒を対象に、例年、高等部職場体験の受入れを実施しています。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
特別支援学校の生徒を対象に、職場体験を受け入れているということです。
大学生向けインターンシップにおいては、障がいの有無は不問とされているということですが、これはホームページ見ると、やはりあまり明記はされていませんので、行ってもいいのかなとか、遠慮してしまうような方もいらっしゃるのではないかと、ちょっと不安に感じております。
障がい者の受入れに積極的であることを周知啓発することで、市民の皆様にも共生社会への本市の姿勢を知っていただけたらと思います。この取組により、障がいのある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えることで、お互いに理解し合っていくことが、共生社会の実現に大きな意味を持つものと考えます。
再質問)インターンシップにあたって、就労支援事業所の支援員との協力は可能か
◆1番(勝股修二) ここで、再質問をお願いいたします。
最近では、大学生のうちから就労支援を受けつつ、就職活動をされている方もいらっしゃいます。そのような方のインターンシップに当たって、就労支援事業所の支援員さんとの協力というのは可能でしょうか、お伺いします。
◎人事課長(山本智子) お答えします。
まず原則としては、学生の方が1人で業務に当たることのできる実習内容を選んでお申込みいただくことになりますが、実習に際し、例えば事前に支援員の方が、学生の障がいの特性を市職員に教えていただくことや、実習中の学生の様子を見に来ていただくことなど、インターンシップが双方にとって、より有効かつ円滑なものとなるよう御協力いただくことは可能と考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
障がい者と一言で言っても、その機能や特性というのは非常に千差万別です。様々な機能や特性を理解をするためにも、専門家である支援員の力もお借りしていただきたいと思います。
⑵ 本市の障がい者雇用について
ア 市内企業における障がい者雇用率について
◆1番(勝股修二) それでは、次の小項目に移ります。
小項目(2)、本市の障がい者雇用について。
本市一般企業における障がい者雇用の浸透度をお尋ねしたいと思います。
ア、市内企業における障がい者雇用率について、お尋ねします。
第7期障がい者計画案において、令和4年度は1.61%ということですよね。かなり低い数字となっておりますが、現状ではどう変化しておりますでしょうか。また、現状では、その数字をどのように評価しておりますでしょうか、お伺いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
尾張旭市内に本社があり、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者の雇用義務のある企業は33社です。
障がい者の雇用率については、ハローワーク瀬戸が把握しており、令和5年6月1日現在、1.90%でございます。前年同期との比較では、0.29ポイント増加しており、企業における障がい者雇用についての理解が進みつつあると感じております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
約0.3ポイント上がったということで、理解が進みつつあるとも評価をできますけれども、法定雇用率にはまだまだ及ばない状況にあります。今後もハローワークと連携をして、障がい者雇用とそれにまつわる諸制度について、周知啓発を図っていただきますようよろしくお願いいたします。
イ 本市市民(手帳所持者)の就労状況について
◆1番(勝股修二) ただいまの質問は、市内企業側から見た雇用率でありましたが、就労問題というのは、本来広域的な問題です。本市市民の就労先は、市外であることのほうが多いので、本市の障がい福祉政策を考えていくためには、市外への就労も含めて考えていかなくてはならない問題です。
そこで、イ、本市市民(手帳所持者の方)の就労状況について、分かる範囲でよいのでお伺いをいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
障害者手帳を所持する方の就労状況について、個々に把握はしておりませんが、ハローワーク瀬戸の調査によれば、令和5年6月1日現在、尾張旭市内に本社のある障がい者雇用義務のある企業は33社あり、そのうち障がい者を雇用している企業が24社、当該企業で働く障がい者数は98人となっております。
一方、次期障がい者計画策定のために、昨年度行った障がいのある方へのアンケート調査では、回答があった1,784人のうち、仕事をしていると答えた方が22.0%、393人となっております。この人数を回答率49.5%で割り戻しますと、単純計算ではありますが、790人ほどの方が、何らかの就労をしていると推計することができるのではないかと考えております。
また、令和4年度に、就労支援事業所から一般就労に移行した方は16人おられました。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
なかなか詳細な評価は難しいようなんですが、就労支援施策を計画していくに当たっては、どのくらいの方が就労希望を持っていて、そのうち一般就労が可能な方というのがどのくらいいらっしゃるかなど、施策検討のためにもう少し就労状況を把握していただければと思います。
⑶ 企業、行政、就労支援事業所等の連携体制の構築について
◆1番(勝股修二) それでは、小項目の(3)に移ります。企業、行政、就労支援事業所等の連携体制の構築についてとなります。
昨年11月の尾張旭市障害者地域自立支援連携会議において、就労可能な方は、職場の近くに住み、収入を得ることが大事であることや、市内の障がい者の方を市内事務所で就労促進するようなツールや環境が整っていないという御発言に対して、連携体制の構築を検討されるとの御答弁がありました。具体的にどのような連携をされるのか、現段階のお話でよいのでお伺いをいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
関係機関との連携という点では、毎年、ハローワークと瀬戸市との共催で、障がい者雇用のための準備セミナーを開催し、特別支援学校と企業とのマッチングや情報共有を図っております。また、障がい者計画等策定会議の場においても、ハローワークから意見をいただくなどして、情報共有及び連携を図っているところです。
次に、就労支援事業所との連携については、障害者地域自立支援連携会議の中の日中活動・就労ネットワーク連絡会において、就労支援に関する課題の抽出や情報共有などを行っています。
しかしながら、障がい者の雇用や就労支援については、様々な課題があり、越えるべきハードルは高いと認識しております。次期第六次総合計画や障がい者計画においても、重点施策として掲げているところであり、今後もハローワークや就労支援事業所との連携を強化するとともに、歩みを前へ進めるという点では、企業との連携についても検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
いろいろと連携をしていただいておりますが、多くの課題、高いハードルを認識されて、重点施策として掲げていただいているということですので、私としても今後注視をしていきたいと思います。
⑷ 就労支援関連事業者に対する支援について
◆1番(勝股修二) 次の小項目に移ります。小項目(4)、就労支援関連事業者に対する支援についてとなります。
もともと障がい者にまつわる施策というのは、措置時代も含めて行政の役割でした。それを民間事業者の活力を生かして、よりよいサービスを提供していこうということで、介護関連事業や福祉関連事業を、営利企業も含めた全ての法人格を持つ団体にその役割を委ねてきたという経緯があります。
しかし、これらの事業は厳格に基準が設定をされて、売上げに当たる報酬も画一的に設定をされています。また、民間事業者の経営努力により、収益率を向上すると、数年に1回の報酬改定により、報酬を減額されてしまいます。昨日の質問にも、訪問介護のところで減額をされたということがありました。
このように営利企業と言いつつも、一概に営利を目的としているとは言えず、公益的な役割を果たしている事業者の一つが就労支援関連事業者であります。
令和元年6月定例会において、就労定着支援の質問があり、非常に成果のあるサービスであると評価をされています。
しかし、現場からは、就労定着支援単体としては、いろいろと負担が大きくて、赤字にならざるを得ない。セットでやっていかないと、とてもじゃないとやっていけないよというような話でした。
令和7年度より始まる就労選択支援、これは様々なマッチングをして、それぞれ就労先、障がい者の方が、お互いミスマッチが起きないように、就労選択を支援していくサービスなんですけれども、それについても、収益性とその負担の大きさからちゅうちょをしているというような声もいただきました。そのような状況において、粉骨砕身していただいているのが現状です。
そこで、営利と言われつつも、実際には公益的な役割を果たしている就労支援関連事業者に対する支援についてお尋ねをしていきます。
ア 周知啓発について
◆1番(勝股修二) まずは、就労支援事業自体についての理解が、まだまだ浸透していない現状において、どのように周知啓発を行っていくのか。
ア、周知啓発についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
就労支援事業所の周知啓発につきましては、福祉課前の通路の一角に、事業所の案内マップやパンフレット、製品を掲示しているほか、福祉のしおりに事業所の一覧を掲載するなどしておりますが、市役所ロビーで月2回開催しているあさぴー福祉市場が、対面でのコミュニケーションを生むことから、啓発効果が高いと考えております。
加えて、特別支援学校や特別支援学級に在籍するお子さんの保護者を対象とした福祉事業所説明会・相談会の開催や、特別支援学校の進路に関する説明会や懇談会に、市と福祉事業所などが参加して、事業所の紹介や保護者への支援も行っております。
市民の皆さんに事業所の存在を知っていただくことは、取りも直さず、事業所の活動を支援することにもつながると認識しておりますので、今後も障害者地域自立支援連携会議の中の日中活動・就労ネットワーク連絡会を活用するなどして、より効果的な周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
様々な周知啓発を行っていただいているということです。御答弁を伺って、ちょっと思いついたのが、地域の病院やクリニックに周知啓発ポスターを貼っていただくとか、もうしていただいているかもしれないんですけれども、支援の対象になりそうな方が行きそうな場所にアプローチをしていくということで、もっともっと効果的な方法についても模索していただけたらと思います。
次に移ります。
イ 働き手の育成について
◆1番(勝股修二) 介護、福祉の関連事業所では、どこも人手の確保が問題となっています。これは、給与水準が低い上に、業務の負担感から働き手が増えないからです。障がい者福祉に関する本市の各種会議の議事録を拝見しても、この問題については把握がされております。
就労移行支援事業所などの指定権者は愛知県になりますので、直接的な関わりはないかもしれませんが、事業所の運営に当たっては、管理者やサービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、就労支援員などの配置を要求されて、それぞれの職責に応じた専門的な資質も必要とされています。
そこで、イ、働き手の育成について、支援することへの御見解をお伺いします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
事業所における職員の確保や質の向上を図るためには、人材育成の観点での事業所支援が重要になると考えております。このため本市では、事業者向けに虐待防止研修などを開催したり、県が実施する専門研修について、事業所職員へ受講を勧奨しています。
しかしながら、事業所から、専門研修の費用が高く、なかなか受けられないという声を聞いており、また、障がい者計画等策定会議の場においても、同様な御意見を伺いましたので、今後は事業所支援の一環として、専門研修の受講費用に対する助成の実施に向けて、準備を進めていきたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) 専門研修の受講費用の助成に向けて、準備をしていただけるということで、本当に心強いお言葉ありがとうございます。ぜひお願いします。
ウ バザー(福祉市場)等の開催について
◆1番(勝股修二) 次の項目に移ります。ウ、バザー(福祉市場)等の開催についてお尋ねします。
就労継続支援などにおいては、外注の仕事などで売上げを出して、A型では賃金として、B型では工賃として利用者さんたちに支給をされます。
愛知県における就労継続支援事業所の工賃(賃金)実態調査において、令和4年度はA型の月額賃金で8万4,030円50銭、時間額で998円60銭、B型月額工賃で1万8,173円80銭、時間額で258円50銭となっています。
A型事業所は雇用関係を取りますので、最低賃金を守らなくてはいけません。ほとんどの事業所が最低賃金の水準で支給されているということが分かります。
どちらの型の事業所も、何とかして利用者さんの工賃や賃金を上げたいということで、仕事獲得のための営業を頑張っていらっしゃるわけです。しかし、支援が必要な方の仕事ですので、納期などに余裕を持たせざるを得ず、仕事の受注にはなかなか苦労をされているということです。
そのような中、工賃を上げるための一つの手段が、バザーなどでの自社製品の販売です。市役所でも、第2、第4木曜日に、1階ロビーにて、あさぴー福祉市場が開催されているので、皆さん御存じかと思います。売上げとしてはそれほど大きくはないですが、利用者さんの工賃を少しでも上げることができるので、非常にありがたいということだそうです。
しかし、この後の質問項目にて出てきますが、文化会館などに人が集まるようなイベントを行っているところでは、営利とみなされて、店を出すことはできないとか、なかなか出店機会が少ないことに困っているようです。
そこで、バザーなどの開催についての支援について、お伺いをいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
福祉市場などについては、事業所の周知啓発の御質問にお答えしたとおり、市役所ロビーで月2回あさぴー福祉市場を開催しているほか、市民祭や健康フェスタなどのイベントに福祉事業所のブースを出店しております。
こうした福祉市場の現場では、物品の販売を通したコミュニケーションが、まさに職業訓練、OJTの貴重な機会となっていると考えておりますので、今後もこれらの取組を継続していくとともに、さらなる拡充に努めてまいります。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
拡充に努めていただけるとのことですが、市内において人の集まるところとは、文化会館はやはり大きいです。拡充に努めていただけることで、文化会館での取扱いもぜひ御検討をいただけたらと思います。
エ 優先調達の推進と受注機会の拡大について
◆1番(勝股修二) 本質問事項の最後の項目に移ります。
先ほどの質問にて、非常に低い工賃にて就労継続支援を受けられていることをお伝えしましたが、現状においてお金になる仕事を得ることは、非常に大変なことです。その中でも、市役所の仕事を積極的に回していこうというのが、優先調達の推進と受注機会の拡大ということになります。
エ、優先調達の推進と受注機会の拡大について、お伺いをいたします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
優先調達につきましては、これまで関係各課と連携を図りながら、全庁を挙げて取り組んでまいりました。その発注実績としては、各種の封筒や再発行用の納付書などの印刷のほか、都市公園の清掃業務委託やリサイクル広場の搬入等に関する業務の委託などがあります。
また、最近の新たな取組としては、保育園の給食用食材としての生しいたけや、市主催イベントの参加賞として、トートバックなども発注しております。
今後も関係各課との連携により、就労支援事業所への新たな業務の創出に努め、さらなる受注機会の拡大を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
優先調達と受注機会の拡大はしっかりされているということで、今後もよろしくお願いします。
しかし、市役所からの発注を増やすのみでは、やはり頭打ちというのがありますし、ほかの事業者さん、一般の事業者さんとの兼ね合いもあります。就労支援事業所が主体的に仕事をつくり出していくことに対して、行政が支援をしていくということが本来の形だと思いますので、これについては、また別の機会に質問をさせていただければと思います。
本質問では、あえて障がい者と呼称される方ということで、回りくどく表現をさせていただきました。最初にお伝えしたように、障がい者とされるのはその時々の社会環境によって変化をしていくからです。発達障がいの方についての理解が浸透して、分け隔てなく過ごせるのであれば、そのような方への特別な支援は不要となりまして、また現在、車椅子で不便な思いをされている方も、道路環境や生活環境が整備されて、車椅子での移動に不自由がなくなれば、そのことについては障がいと言われなくなるという可能性もあります。
最初にお伝えしたように、一億総中流社会と言われた50年前であったら、発達障がい傾向の方でも、普通に中流家庭を築くことができましたし、また今度、産業用ロボットとコンピューターの発達によって、そのような方をはじき出してしまったのが現代なのではないかと考えています。これからはAIの進歩によって、普通程度の知能の方もはじき出されていってしまう可能性があるのではないでしょうか。
本年の1月23日に、「AI発展、世界雇用4割に影響」と新聞報道され、その記事では、国際通貨基金が先進国では約6割の雇用に影響を及ぼし、AIが多くの仕事を代替すれば、新たな社会的緊張を招くと分析をしています。
この就労支援の問題についてみんなで考えて、これからの世界の就労について合意形成を図っていくということは、子供たちやさらにその先の次世代のために、非常に重要なことだと考えています。執行部や市職員の皆様だけではなくて、議員の皆様、またさらには市民の皆様も、これからの社会の形について一緒に考えていただければ幸いです。何とぞよろしくお願いいたします。
では、次の質問事項に移っていいでしょうか。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。