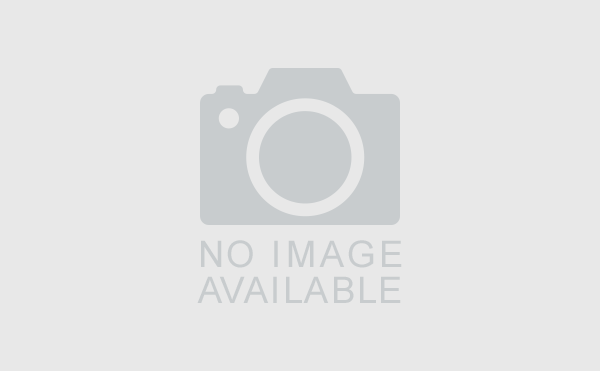地域共生社会や地域包括ケアシステムの実現に向けて、支え合いの実現と想定される危険性について
この質問の要約
質問のテーマ
**「地域共生社会」と「地域包括ケアシステム」の実現に向けた、住民同士の「互助(支え合い)」**の推進と、それに伴い想定される危険性(リスク)への対策について
背景と問題提起
勝股議員は、高齢化に伴う社会保障費、特に介護費用の増大を背景に、制度を持続可能にするためには、公的なサービス(公助)だけでなく、住民同士の助け合い(互助)の仕組みが不可欠であると指摘しました。
しかし、権利意識が高まる現代において、善意の支え合い活動がトラブルに発展するリスクがあり、互助の推進を妨げている現状について、具体的な市の取り組みと課題を質問しました。
主な論点と市の答弁
| 議員からの質問・指摘 | 市(健康福祉部長・市民生活部長)の答弁 |
| 1. 介護施設での事故と苦情対応 施設での転倒事故後、家族から責任を追及されると、事業者は利用者の行動を制限せざるを得なくなる。プロの現場ですらこの状況では、ボランティアによる互助はさらに困難ではないか。 | ・事業所から事故報告書を提出させ、内容を把握し再発防止策を確認している。 ・苦情や相談には、中立的な立場で施設に助言などを行っている。 |
| 2. 「あさひ生活応援サービス事業」の課題 高齢者の「ちょっとした困りごと」を支援する互助事業の課題は何か? | ・ボランティア(支え手)が集まらない。 ・専門知識が必要な依頼や、危険を伴う依頼があり、断らざるを得ない場合がある。 |
| 3. 生活支援コーディネーター第2層の配置 地域の支え合いの司令塔(第1層)はいるが、中学校区などの身近なエリアで活動する第2層コーディネーターが未配置で、事業拡大が困難ではないか。 | ・他自治体の事例も参考に、より効果的な取り組みを進める中で、第2層の配置についても調査・研究していきたい。 |
| 4. 市民活動保険の活用 友人・知人への支援なども、ボランティア団体の枠組みで市民活動保険を使えば、安心して活動できるのではないか。 | ・保険料は市が全額負担している。 ・ただし、特定の個人に対する活動は保険の対象外となるため、活用は難しい。 |
| 5. 認知症高齢者の個人賠償責任保険 認知症の方が起こした事故の損害賠償に備える保険制度が、近隣市では導入されているが、本市で未実施なのはなぜか。 | ・費用対効果や公費負担の是非、事務の煩雑さなどの課題があるため、導入には慎重。 ・ただし、「徘徊高齢者見守り支援シール」の申請時に、個人で加入できる保険の確認や紹介を検討したい。 |
結論と要望
勝股議員は、権利関係が複雑な現代社会で「地域共生社会」の実現は難しいと感じていたが、その必要性を痛感していると述べました。
その上で、市民が主役となり、行政や地域包括支援センターがサポート役として、住民同士が安心して支え合える「仕組み」や「枠組み」を構築することを強く要望し、質問を終えました。
議事録全文
◆1番(勝股修二) 質問事項2に移らせていただきます。
それでは、質問事項2、地域共生社会や地域包括ケアシステムの実現に向けて、支え合いの実現と想定される危険性についてに入ります。
超高齢化社会に向けて、社会保障費の負担が大きな問題となっています。介護費用の総額は14兆円を超え、今後も膨らんでいくと予想され、介護保険料も年々増加の一途をたどっている状況です。現在、国政では、103万円の壁、つまりは手取りや働き控えについての議論が活発に行われていますが、国民の手取りが増えないのは、社会保障費の負担増も大きな原因となっています。介護保険制度は2000年に始まりましたが、当初は0.6%であった2号被保険者の保険料率は、今年度において1.6%と2.5倍になっています。
平成24年8月に施行された社会保障制度改革推進法において、第2条1項「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。」、同2項「社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること。」とありますように、これ以上の社会保障負担の増加を抑制し、次世代への負債を残さないためには、助け合いの仕組みである地域共生社会の実現や地域包括ケアシステムの構築が不可欠であると言われています。
しかし、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みである互助を実現していくに当たって、昨今の権利意識の高まりにより互助を妨げる様々な問題も生じています。
そこで、地域共生社会の実現と地域包括ケアシステムの構築への本市の取組と、互助において想定される危険性について、項目ごとに質問をさせていただきます。
(1) 介護施設等における事故と苦情相談対応について
◆1番(勝股修二) 小項目1に入ります。
まずは、介護の現場における現状について確認をしていきます。転倒事故など避けられない事故がしばしばあると思いますが、本市として、転倒事故などについて把握をされているのか、また、本市は苦情相談窓口になっていると思いますので、それに関する苦情の申出があるのか、もしあったとしたら、どのように対応されているのか、小項目1、介護施設等における事故と苦情相談対応についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
介護施設等における事故により医療機関で治療を受けた場合などは、事業所から事故報告書を提出していただき、事故内容の把握や再発防止策を確認しております。また、事故に対して苦情や相談を受けた場合は、事故報告書に基づき、施設側に詳細を確認した後、本人や御家族などからの相談内容に応じて、適宜、施設に対して助言等を行っております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
中立的な立場にて助言などを行っていただいていると思います。介護の現場においてはありふれたことなんですが、通所施設や入居施設などにおいて、不幸にも転倒して骨折してしまったときに、御家族や御親族の方が事業者に対して責任追及をされることがあります。いわく、通所中や入所中は管理下にあるのだから、転倒させてしまった責任を取ってほしいという御主張です。金銭面のみならず、一部に責任の追及や謝罪の要求などがあることもあります。こうなりますと、事業所としても非常に大変な思いをするわけで、何としても転倒をさせない方向に動いてしまい、つまりは利用者さんに対して、「立たないでください」、「歩かないでください」、「トイレに行きたいときは呼んでください」と言って、もう自由に動けなくなってしまうわけです。
するとどうなるかというと、要介護の高齢者の方々は、さらに足腰が弱っていきます。高齢者の特性や疾患についての不理解や対応の誤りにより、双方にとって不幸なことが起こっているわけです。動かなければ弱りますし、動けば事故が起こる可能性というのは必ずあります。業務として行っている介護サービス事業においてこのような状況ですので、無償や実費弁償程度で損害保険などの後ろ盾もないボランティア活動では、及び腰になってしまい、互助の実現はもう非常に困難になってしまう可能性があるのではないでしょうか。
(2) あさひ生活応援サービス事業について
◆1番(勝股修二) 小項目2、あさひ生活応援サービス事業についてに入ります。
本事業は、本市の生活支援体制整備事業により、尾張旭市社会福祉協議会に委託された生活支援コーディネーター事業の一環で行われる事業です。この事業は、尾張旭市社会福祉協議会のホームページによると、「ご高齢のかたが、住み慣れた地域でその人らしく安心した生活を送ることができるよう、日常生活上のちょっとした困りごとを解決することを目的とした、互助の精神を基調とする住民参加型の非営利の生活支援活動です。」とあります。事業規模から考えると、生活支援コーディネーターの活動理念にある、支え上手、支えられ上手を増やすことに向けた互助の普及に向けた入り口の事業であると考えます。
ア これまでの事故事例について
◆1番(勝股修二) そこで、互助の普及に向けての問題点を探っていくために、ア、これまでの事故事例について、傷害補償や賠償責任補償の保険を利用するような事故や、その一歩手前のような事象がなかったかお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
あさひ生活応援サービス事業における事故としましては、これまでに1件、ボランティアの方が作業中に照明器具を破損し、補償のため保険を適用した事例がありますが、これ以外に保険を利用するような事故等は起こっていないと聞いております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
現在のところ、大きな事故はないということで安心をいたしました。
この事業は、先ほどお伝えしたとおり、その事業規模から互助の普及に向けた入り口であり、テストケースであると個人的には考えています。現在、大体年間延べ230件ぐらいですかね、それで尾張旭市の高齢者の方々のお困り事が大部分、じゃ、解決できているかというと、そういうことではなくて、本当に一部のお困り事の解決の状況であると思います。
イ 事業実施における問題点(困り事)について
◆1番(勝股修二) そこで、制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共につくっていく社会である地域共生社会を実現していくためには、現状での問題点をしっかり把握しておくことが必要です。
そこで、あさひ生活応援サービス事業における、項目イ、事業実施における問題点(困り事)についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
事業を実施する上での問題点につきましては、大きく2つあると考えております。
1つ目は、当該事業を支えていただいているボランティアの方がなかなか集まらないことです。毎年、ボランティアである生活応援サポーターの養成講座を開催しておりますが、参加者を募集しても集まらず、昨年は、講座を3回予定しておりましたが、1回中止して2回の開催となりました。今後は、周知の方法等にさらなる工夫が必要であると考えております。
2つ目は、依頼される援助の内容が難しい場合があることです。この事業は、ボランティアの方が高齢者の日常生活上のちょっとした困り事を解決することを目的としておりますが、時にボランティアでは対応しかねる専門知識が必要な援助や危険を伴う援助の場合があり、そうした場合は、やむなくお断りをしております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
1つ目は、支え手である生活応援サポーターが集まらないという問題、2つ目は、受け手としての援助を受ける側の問題であるようです。御答弁いただいた問題点により、地域での支え合いの輪がなかなか進みにくい状況ですが、このような中で、支え合い、お互いさまの考えを根づかせるために粉骨砕身で努力をしているのが生活支援コーディネーター、別名、地域支え合い推進員です。
(3) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)第2層の配置について
◆1番(勝股修二) 小項目3に入ります。
あさひ生活応援サービス事業は、生活支援コーディネーター事業の一環であることは先ほどお伝えしましたが、ここで生活支援コーディネーターについて改めて確認をしておこうと思います。生活支援コーディネーターとは、厚生労働省によると、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすものを生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)とするとされています。括弧書きで地域支え合い推進員とあるように、地域での支え合いである互助を推進し、支え上手、支えられ上手になれるように、優しいつながりのある地域へ推進する役割を持っています。
その具体的な働きは、日常生活ニーズ調査や地域ケア会議などにより、地域の高齢者支援のニーズ及び地域資源の状況について十分把握し、地域のニーズと資源の見える化、ボランティアや介護保険外サービスなどの地域資源の掘り起こしを行った上で、ニーズとサービスのマッチングをしていく役割を持っています。
構造的には、生活支援コーディネーターは3層に分けられており、第1層は、市町村全域、尾張旭市全域で問題把握や資源の掘り起こし、ネットワーク化をする司令塔の役割を果たします。第2層は、日常生活圏域、つまりは中学校区の範囲において地域資源の掘り起こしをしつつ、ニーズとサービスのマッチングを行う役割を持っています。現在は、多くの市町村が第2層までです。急に始めても、なかなかこれ非常に難しい事業なので、しっかり構築がし切れないということで、今のところは第2層までの整備を市町村は求められているというところです。ちなみに第3層は、小学校区エリアで細かい地域を見ていく地域支え合い推進員を設置していくという制度になっています。
現在は、多くの市町村が第2層までの機能の充実に取り組んでいるところですが、ここで尾張旭市の現状を見てみますと、現在設置されているのは第1層のみであり、委託を受けた社協さんの第1層が全てを担っている状況です。本来は司令塔としての役割を果たさなければいけないところ、あさひ生活応援サービス事業における個々の訪問調査によるアセスメントや注意事項の説明、サービスのマッチングからアフターフォローまで全てを担ってみえます。正直なところ、マンパワーからもこれ以上の事業拡大は困難な状況と考えますが、これまで整備されてこなかった第2層の配置についてはいかがお考えでしょうか。
小項目3、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)第2層の配置についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
本市では、地域住民やボランティア、NPO、医療機関など、多様な主体と連携しながら、支え合いの仕組みを構築し、地域資源やニーズの把握、担い手の発掘・養成などにより、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進しております。
具体的な取組としては、あさひ生活応援サービス事業を利用して、地域住民への普及啓発等を行いながら、援助をお願いしたい高齢者と援助活動をしたい方が互いに助け合える体制づくりを進めております。
今後は、これまで整備してきた体制の検証を行うとともに、第1層と連携すべく第2層にも生活支援コーディネーターを配置している他自治体の事例も参考にしながら、地域共生社会の実現に向けたより効果的な取組を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
明確というか、第2層をすぐに設置するというような答弁ではなかったと思いますが、より効果的な取組を進めていくということですね。私も何でもいいから第2層をつくってほしいと、そういう気持ちはございません。ほかの自治体の様子を見ますと、国の方針に基づいてとにかく整備をしてくださいと、国からの要請があって整備をしてみました。でも、うまく動いていませんというような自治体は、結構そこかしこに見られるような気がします。
その中でも先進事例として挙げられる豊明市の豊明モデル、これ私、昔からの知り合いが結構中心にやっているんですが、これ藤田医科大学というのが本当に大きな働きをしていて、うちとはやっぱりリソースそのものが違うというところもあって、第2層がすぐこうしっかりと稼働していくためには、なかなか難しい問題をはらんでいるなとは思いますが、しかし、本市は地道に生活支援体制整備事業を進めてきて、本定例会の補正予算案にて、この生活支援コーディネーターに対する増額補正、人件費の増加補正が行われるぐらいにちょっとマンパワーが不足してきているところなんです。本取組をさらに広げていきたいということで、広げていくためには、今後、第2層の設置についても、おいおいこの事業の拡大に合せた第2層の設置を御検討いただけるよう何とぞよろしくお願いいたします。
(4) 市民活動保険の活用について
◆1番(勝股修二) 小項目4に入ります。
先ほどお伺いした生活支援コーディネーターの果たすべき役割の一つに、生活支援の担い手の要請やサービスの開発といったものがあります。これは公的支援以外のインフォーマルなサービスであり、その中の一つに地域での支え合いをするボランティア団体などの発掘や支援も含まれると思います。現状において、知人や友人の支援というのは、何の枠組みもなく行われていると思いますが、先日にも市内にて不幸な事故があったことは皆さんも御存じのとおりだと思います。本当に御冥福をお祈りしたいと思うんですが、人が動けば事故は必ず起こり得るものです。このような危険性に対して備えておくためにも、知人や友人の支援においてボランティア団体の枠組みの中で行うことができれば、より安心して行うことができるのではないでしょうか。
本市のホームページを拝見しますと、市民活動保険の補償の対象となる活動の一覧に、「2、社会福祉・社会奉仕活動」という区分があり、「在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ」が具体例として明示をされています。
そこで、互助における危険性に備えるために本保険の活用は可能なのか、可能であればどのような条件か、また、活用するとしたら市の負担はいかほどかについて、小項目4、市民活動保険の活用についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
市民活動保険は、ボランティア活動など地域のために行う活動中における万が一の事故に備えるための保険です。保険料は、市が全額負担しており、けがをされたり物を壊してしまった場合などに保険金が支払われております。対象は、尾張旭市に活動拠点を置く自治会や町内会、子ども会、市に登録されているボランティア団体などで、その中には社会福祉・社会奉仕活動を行う団体も含まれております。しかしながら、この保険は、無報酬で行う公共的・公益的な活動が対象となりますので、特定の個人に対する活動は保険の対象外となります。
なお、この保険は、毎年入札によって契約しており、年間の保険料は約120万円となっております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
保険って本当に難しくて、対象者とか実際に支払われる場合の条件とかなかなか明確には本当に言えないというか、言ったとしたら、その後保険料が出なかったときに、じゃ、どうするんだとか、そんな問題にもなってくるので、これ、なかなか難しいんですけれども、友人や知人への支援を入り口にしつつも、対象者を特定しない団体でのボランティア活動につながることが理想かと思うんですが、しかし、訪問ヘルプやガイドヘルプを目的としたボランティア団体って、昔、結構あったんですけれども、かなりの部分、介護保険サービスとか、身体障がい者のサービスに移行をしてしまったということで、互助が共助のほうに移行してしまっているというところもあります。つまり互助としてのボランティア団体としての存続はかなり難しいことのようですので、市民活動保険の活用は現実的ではないと思いました。
再質問)サロンや筋トレクラブは市民活動保険の対象か
◆1番(勝股修二) ここまで質問して考えてみますと、互助におけるリスクを軽減するということは、かなりの難題であると痛感をいたしましたが、念のため再質問をお願いします。
互助が行われる場合は、さっきの生活支援コーディネーターにおける支えあいサロンとか、当市の場合だと誇るべき筋トレ、らくらく筋トレクラブなんかもあります。そういうのも互助の場ではありますが、こちらは補償対象でしょうか、お伺いをします。
◎市民活動課長(坂田みどり) お答えします。
地域で行われる高齢者対象のサロン等の活動についても、長寿課等から対象となる団体として報告のある団体を保険の対象としております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございました。対象となるということで。
(5) 認知症高齢者等個人賠償責任保険について
◆1番(勝股修二) 最後の質問は、これまでとは多少趣旨がずれますが、小項目5に入ります。
地域共生社会の実現のためには、転倒事故などの比較的小規模なもの以外も認知機能面により引き起こされる可能性のある事故などの危険性にも備えておく必要があります。2007年12月の愛知県大府市における鉄道事故は、列車遅延による多額の損害賠償請求があったことから、非常に大きな話題になりました。これは最終的には、最高裁判所において、大丈夫だったようなんですが、やっぱりただ、今も認知症の方と一緒に暮らしてみえる御家族の方が、やっぱり大きな憂いが残ってしまっている状況です。それに対して多くの自治体が備えて、近隣の瀬戸市や長久手市でも実施されている認知症高齢者等個人賠償責任保険制度は、本市では実施をされていません。
そこで、まずは、本制度が未実施となっている理由について小項目5、認知症高齢者等個人賠償責任保険についてお伺いをします。
◎健康福祉部長(臼井武男) お答えします。
認知症高齢者の行動が原因となる事故やトラブルに対応するため、県内でも多くの自治体が、民間保険を活用した事故救済制度を導入していることは承知をしております。
しかしながら、令和3年に大手シンクタンク企業が行った自治体による認知症の人の事故を補償する民間保険への加入支援に関する調査研究事業では、認知症高齢者やその家族の安心につながる成果が確認されている一方で、自治体における課題として、費用対効果や公費負担の是非、事務手続の煩雑さなどが報告されております。
これらの課題に加え、やはり市が公費を負担する以上、その負担が高齢者全体、ひいては市民全体の福祉向上に効果があるか否かを総合的に判断する必要もあると考えております。
したがいまして、直ちに導入の可否を決定することなく、既に導入している他自治体の事例や効果を参考にしながら、調査研究を継続してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
現在のところ、制度の導入にはどちらかといえば否定的であるようなんですが、認知症を患われた方やその御家族は今も地域で暮らしています。いつ事故やトラブルに遭うかは分かりません。
再質問)認知症の恐れのある方に個人賠償責任保険を紹介することは可能か
◆1番(勝股修二) そこで、再質問をお願いします。
それらに対応することのできる個人賠償責任保険や個人賠償特約というものがあり、自動車保険とか自転車保険に附帯をしています。これ、御家族の1人でも入っていれば大丈夫な保険なんですが、これを紹介するとか、入っているか確認するということはできますでしょうか。お願いします。
◎長寿課長(岡田和也) お答えします。
本市では、徘回するおそれのある高齢者を対象に「はいかい高齢者おかえり支援シール交付事業」を行っており、これまでは確認を行っておりませんが、今後は申込みの際に個人賠償責任保険の加入について確認や紹介することも検討したいと思います。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
ぜひ確認や紹介をお願いいたします。その際には、認知症初期集中支援チームなんかとも連携していただいて、徘回事業だけでなくて、そのほかの認知症の方にも行き渡るようなことがしていただけたらなと思います。正直なところ、初めて地域共生社会というのを聞いたとき、この権利関係とか法律にがちがちに縛られた現代社会において非常に難しいんではないかなと、簡単に言ってくれるなと思ったもんですが、しかし、様々な経験をするうちに地域共生社会の実現は本当に必要なのだと実感しました。本当は地域共生社会というのは、あくまで一人一人の市民が主役であって、行政や地域包括支援センターというのはサポート役となります。市民相互が安心してお互いを支え合えるようなその仕組みや枠組みを構築していただきたいと思います。
これにて私の一般質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。