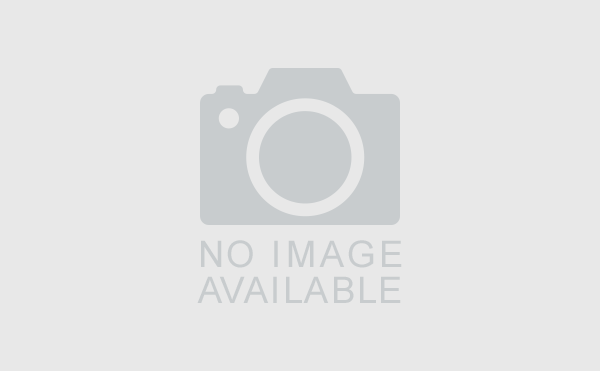本市における産業振興の今後の展望について
本市における産業振興の今後の展望について
この質疑では、尾張旭市の地域経済が抱える課題と、その活性化に向けた具体的な方策が議論されました。
地域経済の現状と課題
勝股議員は、本市がベッドタウンとしての特性が強く、市民の消費が市外へ流出している現状を指摘しました。地域経済分析システム(RESAS)のデータに基づき、地域内でのお金の循環を示す地域経済循環率が年々、加速度的に低下していることに警鐘を鳴らしました。
市の答弁では、この低下は住宅都市としての特性上、市外からの所得流入が増える一方で、市民の市内消費が減少したことが主な要因であると分析。今後は、消費の流出を抑制し、バランスの取れた経済循環を目指す必要があるとの認識を示しました。
市の取り組みと実績
市の産業振興策について、具体的な実績と今後の展望が議論されました。
- マネーの歩留まりを高める業種: 市は、特定の業種を挙げることは避けつつも、市の特性に合わせて小売業やサービス業などの第三次産業を中心に、地域資源を活用することが効果的であるとの見解を示しました。
- 異業種交流会(Meet up ASAHI):
- 実績: チャレンジ事業として開催され、延べ154人が参加。市内事業者同士の新たな取引(設備のメンテナンス、広告デザインの作成など)や、ふるさと納税の返礼品開発といった連携が生まれたと報告されました。
- 今後: 行政主導の開催は予定していないものの、成果を報告書として市のホームページで公開し、民間での自発的な動きを後押ししたいとしています。
- 創業支援:
- 実績: 商工会や金融機関と連携した創業支援事業では、相談件数やセミナー参加者数が目標(年間100件)を上回り、実際の創業者数も目標(年間24件)を超える30件(令和5年度)に達しました。特に介護福祉や飲食などのサービス業での創業が多いことが特徴です。
- 課題: 創業後の長期的なフォローアップ体制の構築や、新規創業者が直面するテナント料の負担といった課題が浮き彫りになりました。市内の貸テナントは数が少なく、賃料も高めであるため、個人での起業のハードルになっていると指摘されました。
議員からの新たな提案
質疑の最後で、勝股議員は現代の起業スタイルに合わせた新しい支援策を提案しました。
- 週末ビジネスプランコンテスト: 本市のベッドタウンという特性を強みと捉え、週末のみのビジネスに特化したコンテストの開催を提案。
- 新しい形の起業支援: 自宅サロンや週末だけの店舗など、低リスクで始められる小規模な起業がトレンドであるとし、空き店舗や古民家を安価に活用できるような支援の必要性を訴えました。
- 自然を生かした産業振興: 近隣市に大型商業施設が多い中、本市は無理に競争するのではなく、公園などの自然豊かな空間を活用してお金を使ってもらう仕組みを考えるべきだと述べ、次の公園利活用の質問へと繋げました。
議事録全文
◆1番(勝股修二) ただいま議長よりお許しがありましたので、通告に従い、順次質問をさせていただきます。愛知維新の会尾張旭市議団の勝股修二です。
今回は、2項目を立てさせていただきました。
昨年12月の一般質問にて私、かなりお見苦しい姿をお見せしたと思いますので、今回はかなりコンパクトに、短い時間で終わるように行ってまいります。
それでは、質問事項1、本市における産業振興の今後の展望についてに入ります。
本市は、就業者の6割以上が市外で働くことで、雇用者所得はかなりの割合を他都市から得ており、市外で働き、市内でくつろぎ休む、ベッドタウンとしての特性を非常に強く持っています。市外で稼いだお金を市内で余暇やレジャー、外食、はたまた買物等で消費することができれば、市内にお金を残すことができ、市内経済が循環する。つまりは、市内での金回りがよくなるのではないかと考えます。
しかし、内閣府などが提供する地域経済分析システム(RESAS)の2018年の数字を見ますと、民間消費額の支出流出入率がマイナス27.1%と、全国1,741市区町村中1,536位となっており、すてきな店が少ない、好きな店がないと、令和4年市民アンケートにあるように、市内で余暇やレジャー、外食などの消費支出がしにくいことを示唆しています。
地域の経済自立度を表す地域経済循環率が、2010年には73.1%、2013年は72.6%、2015年は70.2%、2018年に至っては62.5%と、加速度的に低下をしています。本当にここの間はだっと下がりましたけれども、ただ、さすがにこれ以上加速はせずに、ちょっと底打ちをするんじゃないかなと私自身は見ているんですが、この間、じゃ、何があったかというと、やっぱり市外に大きなショッピングセンターがたくさんできてきたような時期だったのかなとも思います。
この数値は、随時修正がかかるようで、この後に出てくる報告書とは少し違っていますが、現時点での数値を示させていただきます。
このような中、本市における産業振興の今後の展望について、項目ごとにお伺いをしていきます。
本市では、産業振興について、令和4年2月に尾張旭市産業振興基礎調査を報告し、本報告書の第3章の3項(4)において、2015年のRESASのデータを基に様々な分析がされています。しかし、2018年のデータではさらに大幅な低下が見られました。本報告書作成の、これ4年前のデータになっていて、ちょっとデータがどうしても時間差がある分だけ古くはなってしまうんですが、この下がったことについては、どのような分析をされておられるのでしょうか。
小項目1、地域経済循環率の更なる低下について、本市の受け止めをお願いいたします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
地域経済循環率は、地域内で生み出された所得が、その地域内でどれくらい循環しているかを示す指標であり、それぞれの自治体の特徴を表すものとなっております。
本市における地域経済循環率の低下については、住宅都市の特徴の一つと言える市外からの所得流入が増加したことに加えて、市民の市内消費が減少したことが要因と考えられます。
地域経済循環率は、様々な要因によって変動しますが、消費、支出、投資の流出抑制を図り、バランスの取れた経済循環を目指すことが重要であると考えております。そのため、本市の住宅都市としての特性を踏まえつつ、市内事業者への支援や事業者同士の取引を促進させながら、地域経済の活性化を図っていく必要があると考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
市内事業者の支援や市内事業者同士の取引を促進していく必要性を御認識いただいているということですが、この市内事業者というのは、これから市内事業者になっていこうと、これから創業しようという方も含んでいると理解をしますが、もし認識に間違いがありましたら、この後の御答弁にて付け加えていただければと思います。
次の小項目に移ります。
先ほどお伝えしたように、本市はお金を外部から獲得しているけれども、流出量も大きい状況です。本報告書には「消費・支出・投資の外部流出の抑制とともに、市外からの“外貨”を稼ぐ産業の誘致や育成を図り、マネーの歩留まりを高めることにより、地域経済循環率を向上させていくことが求められる。」とあります。外部流出を抑制し、あるいは市外から外貨を稼ぐ産業で、本市の現状から見て効果的と思われる業種や業態はどのようなものと分析しておられるのでしょうか、小項目(2)マネーの歩留まりを高める業種、業態についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
令和3年度に公表しました尾張旭市産業振興基礎調査報告書においては、資金効率や収益性、いわゆるマネーの歩留りを高めるために、効果的な業種や業態の特定はしておりませんが、本市は、就業者の割合が第三次産業に多いことや、特定の業種に依存していない産業構造となっております。
このため、市の特性に合わせて、地元の小売業やサービス業などの第三次産業を中心に、市内の地域資源の活用を図ることで一定の効果が現れると考えております。具体的には、小規模企業等補助金などの補助制度を活用して、販路拡大や人材育成などの支援を継続していくとともに、市内の事業者同士の取引を促進する取組を推進していく必要があると考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
確かに一次産業というのは土地が必要ですので、現状から拡大していくことはちょっと難しいのかなとも思いますし、二次産業については供給連鎖ですね、サプライチェーンと言われたりしているんですが、また通勤範囲とかを考えると、交通網や流通網が発達した現代においては非常に広域化していて、域内だけの話ではなく、言い換えると、現在の二次産業や製造業などは、工場は市内にあるけれども、原材料は市外から調達、従業員は市外在住者が結構多くいて、稼いだ分、利益の部分についても、大分本社の本社所在地のほうにマネーが流れているというような形でですね、なかなか市内に落ちる所得はあまりないのではないかというのを実感しているところです。土地があれば産業を集めて集積化することで、域内取引、地域内での取引が活発化して経済効果が大きくなるということはありますが、こちらもちょっと土地の余っていない本市では非現実的ですし、ベッドタウンとしての生活環境のよさというのを損なってしまう可能性もあります。そうなると、御答弁にありましたように小売業やサービス業などの第三次産業をいかに伸ばしていくかということなのだと考えます。
次の小項目に移ります。
令和5年9月の補正予算にて、チャンレジ事業として産業振興ネットワーク形成事業が始まり、令和6年1月より5回にわたってMeet up ASAHIという異業種交流会が催されました。私は残念ながら参加することがかなわなかったんですけれども、この中にも何人か参加して見えた方がみえたと思います。今年の初めに展示してあった写真を拝見すると、とても盛り上がっていたようで、今後がとても楽しみな活動だなと思いました。しかし、市の事業である以上、今後、事業評価が行われると思いますが、ひとまず先に交流会の実績をお聞きしたいと思います。
また、本事業は、市内取引を促進し、地域内経済循環を促進することも目的だと思います。
そこで、実際に本交流会において新たな取引が生まれたのか、具体的なことは企業秘密などもあると思います。本市で把握している範囲で、出してもよい情報だけで大丈夫ですので、小項目(3)異業種交流会の実績についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
チャレンジ事業として、令和6年1月から11月にかけて5回にわたり開催した異業種交流会は、特定のテーマに基づいたセミナーを同時に開催し、参加者の交流を促進しながら実施し、延べ154人の方々の活発な交流が行われました。
交流会における取引の事例につきましては、その後も参加者と継続的に情報交換を行う中で、事業用設備のメンテナンス、広告デザインの作成、セミナー講師の派遣など、市内事業者同士の取引を確認しております。
そのほか、ふるさと納税の返礼品など、新たな事業連携につながった事例もあり、事業担当課と市内事業者との関係構築にもつながっております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
市内事業者同士の新たなつながりをつくることができたということで、チャレンジ事業としての一定の結果が得られたということです。今回は、まずは始めていこうということで行政主導の交流会となりましたが、本来の異業種交流会は、経営者などがビジネスチャンスを求めて、参加費をちょっと多めに払ってでも積極的に参加、開催するものなのだろうなと、私自身今までの経験で思いますし、実際に名古屋などでは非常に多くの交流会が頻繁に行われているということもあります。尾張旭の事業者さんも名古屋での交流会に多くの方が参加されていると思います。私自身も、昔名古屋の交流会で尾張旭の方なんですねという、お会いしたことがありますので。今後は民間で自走していく仕掛けづくりをぜひお願いしたいところですが、ここで再質問をお願いします。
今後の異業種交流会の見通しについてお伺いをします。
◎市民生活部次長兼産業課長(佐藤元昭) お答えします。
産業課がチャレンジ事業として実施いたしました異業種交流会については、今後の開催の予定はございませんが、これまでの交流会の様子や成果などについては、報告書にまとめた上で市ホームページに公表を予定しております。今後、同様の取組を検討される方々の参考にしていただき、新たな動きが生まれることを期待しております。
また、事業者同士の交流の方法は、交流会形式に限ったものではありませんので、商工会をはじめとした団体や事業者との情報交換の中で、事業課題の解決につながるような事業者のマッチングにも取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
いろいろまとめていただいてホームページで公開することによって、同じような形、あるいはまた、もっとうちのほうがうまくやれるんじゃないかみたいな方にいろいろ出てきていただいて、そういうような市内の事業者の交流みたいなのにつなげれば本当にいいのではないかなと思います。どうもありがとうございます。
では、次の小項目に移ります。
本市では、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、創業支援等事業計画が作成され、地域における創業を促進するため、民間の創業支援事業者、こちらは尾張旭市商工会、瀬戸信用金庫、日本政策金融公庫が連携事業者のようですが、これらの事業者と連携してワンストップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催などの創業支援が実施されています。この令和元年に変更認定された事業計画によると、年間目標数として創業支援対象者数が100件となっているようですが、この目標値に対して実績値はいかがでしょうか。まずは小項目(4)創業支援等事業における実績について、ア、創業支援等事業への参加者について、年ごとの実績値をお伺いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
本市では、平成28年度に産業競争力強化法に基づき、国から創業支援等事業計画の認定を受け、尾張旭市商工会、瀬戸信用金庫、日本政策金融公庫と連携して、創業に関する相談窓口の設置や、基礎知識を学ぶ創業セミナー、セミナー受講後のフォローアップを行う、創業フォローセミナーを開催しております。
計画の中では、年間目標数として創業支援対象者数を100件と定めており、その内訳は、本市を含む各連携機関への相談件数と、創業に関するセミナーへの参加者数となっております。
過去3年間の実績といたしましては、令和5年度は108件、令和4年度が144件、令和3年度が101件となっております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
複数の事業ですし、複数の場所で行われる事業ですので、延べ数ということで、ここに行った方とかここに行った方みたいな感じで本当に延べ数にはなっていると思いますが、きちんと計画は達成というか、上振れして達成をできているということです。
同様に創業者数の年間目標数も設定されているんですが、こちらは24件となっています。こちらは、創業支援を受けた方のうち何人が実際に創業されたのかということでそういう目標だと理解していますけれども、また、小項目(2)でお伺いしたように、マネーの歩留りを高めやすい業種についてはどの程度起業されているのかもお教え願いたいので、イ、創業につながった件数と業種についてお伺いします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
先ほど答弁させていただいた令和5年度に創業支援を行った108件のうち、創業につながった件数は30件となっております。
業種別での内訳といたしましては、介護福祉、飲食などのサービス業が24件、不動産業が2件、製造業が2件、小売業が1件、運輸業が1件です。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
年間30件ということで、こちらも計画が上振れして達成しておられるということで、ただ、年間で介護福祉、飲食などのサービス業が24件も創業しているという、ちょっと見てびっくりはしたんですけれども、どちらでやってみえるのかなともちょっと思ったりするわけですが、またいろいろ探してみたいと思います。
また、マネーの歩留りを高めるのではないかと分析しておられる業種ですね、今の介護福祉、飲食等のサービス業についても一定数の創業があったということで、創業支援についても一定の効果が出ているのかなとも思います。
ただ、しかし、起業後の継続率や倒産率というのをネットで検索すると、1年後には9割以上の事業主は継続しているというデータがあったり、1年後には6割しか継続していないよとか、はたまた、実は4割ぐらいしか続いていないんじゃないかというような、いろんなデータがいろんなホームページが出てきて、実際にはどの数字が正しいんだろうと悩んでしまいますけれども、これについては景気や社会情勢などにより大きく左右されるかと思いますので一概には言えないのだと思いますが、では、実際に本市ではどうなっているのかというところで、創業支援を受けた方の事業は継続しているのか、ウ、創業後の経過についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
創業後の経過につきましては、創業セミナーを受講された方を対象に、受講された翌年度の5月にその後の状況をお伺いしております。
以前は、継続的な状況確認は行っておりませんでしたが、令和5年度からは、創業セミナー開始時からの受講者を対象にさらなる創業等の支援を目的とした創業フォローセミナーを実施しており、参加いただいた方には現在の状況などをお伺いしております。
議員が言われるとおり、創業支援を受けて起業された方の中には、その後の事業継続が困難になられる方もお見えになります。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
なかなか実数については把握がしづらいのかなとも思いますけれども、創業支援セミナー参加者については翌年度の5月頃に確認されているということに加え、昨年度より創業フォローセミナーによりフォローアップもされているということです。ただ、長期的なフォローアップは行っていない、あるいは行っていなかったのかなということで、行政として関わった以上は、その取組がどのような効果を及ぼしたのか、分析して今後の取組に生かしていくことが必要だと考えます。特に創業や商業活動による経済効果はちょっと長期的なものになると考えますので、今後は、より長期的な追跡調査と分析、また、創業後の経営支援というのも併せてより積極的に行っていただけるよう要望申し上げます。
次の小項目に移ります。
この項目では、創業支援におけるより具体的な項目の一つをお伺いしたいと思います。
創業時には多額の資金と大きなリスクを背負う覚悟が必要です。小規模店舗であっても毎月かかるテナント料というのは、小規模事業所であるほどかなりの割合を占める負担となります。そのため、起業を考える方はその立地条件などによって得られる利点と、費用負担のバランス、いわゆるコストパフォーマンスをしっかりと考えて創業計画を立てていくわけですが、まずは借りることのできる物件がなければ検討することもできないと、なかなか市内にないから、じゃ市外でやろうかなとか、そういうことにもなってしまうと思います。
そこで、市内において貸テナントというのはどのように分布しているのか、物件数は足りているのか、他市と比較して相場はどのようなものか、小項目(5)市内の貸しテナントについてのア、現状についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
市内の貸テナントの現状につきましては、詳細な情報まで把握しておりませんので、不動産情報を確認した結果についてお答えをさせていただきます。
現状、貸テナントは、名鉄瀬戸線の駅周辺や国道363号線などの幹線道路の近くに多く見られ、入居者を募集しているテナント数は現時点では10件ほどでございました。
賃料の相場につきましては、貸テナントの情報がない地域もあり、駅からの距離や建築年数、周辺環境などにより異なるため、一律に他市町と比較することはできませんが、賃料の坪単価だけで見てみますと、名古屋市に近づくにつれて高くなっていく傾向が見受けられます。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
不動産の管理というのは自治体の業務ではないので、なかなかその辺り難しいかなと思いますけれども、ただ、産業振興をしていくに当たって市内の実情を把握するというのは重要だなと考え、あえて質問をさせていただきました。
大企業によるチェーン店であれば、土地取得から店舗建築まで行うことができますが、資本力のない個人創業だとそういうわけにはいきません。最近の地域づくりのトレンドでは、資本力のない個人が活動の中心となるため、店舗の設備をそのまま使う、いわゆる居抜き物件や、賃料の安い古民家をDIYなどで自分でリフォームして店舗化するというようなのが多い印象です。私も市内のテナントを調べてみた限り、数十万円の賃料でそれなりの大きさの店舗がやっぱりほとんどなのかなと思いました。そうなると、かなりの覚悟を持って借りなければいけない物件なのかなとも思います。
貸テナントというのはあくまでも民間の商業活動ですので、行政がコントロールできるものではないことは重々承知をしています。しかし、創業支援、産業振興の観点から、何らかの関わりはできないでしょうか、イ、支援の可能性についてお伺いをします。
◎市民生活部長(大津公男) お答えします。
事業者の新規出店には様々な負担を伴うため、貸テナントの活用に関する支援を行うことは、事業者の負担を軽減するだけでなく、事業開始の段階から関係づくりを進められるといったメリットもあります。
また、市内における消費拡大や、新たな雇用が創出されるなどの地域経済の活性化にもつながると考えておりますので、ほかの支援策と合わせ、他自治体の事例なども参考にしながら、本市の状況に合った方法について調査研究してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆1番(勝股修二) ありがとうございます。
本市の状況に合った方法について調査研究をしていただけるとのことで、ぜひよろしくお願いいたします。
テナント代が高いとか、かなりの覚悟が必要だとか、こんな話をしていると起業家の先輩方にちょっと、何甘いことを言っているんだということでちょっと怒られてしまうかもしれませんけれども、個人の起業については、大きくこちらも時代が変わっているのではないでしょうか。戦後から高度経済成長期に商売をしていた方のお話は今とは全く状況の違うものでした。今の時代は物が豊富にあって、小売や飲食などは大企業によるノウハウと効率化が出来上がってしまっています。地域での最近の起業は、地域貢献やライフスタイルの充実を目的にしており、少ないリスクでまずは始めてみようといった傾向に感じます。特に自宅でサロンを開いたり、占い師や出張美容など、本当に今、身一つで始められたりするような起業が多いんじゃないかとも感じております。
このような状況の中、地域の創業支援のために全国各地で自治体主催の多くのビジネスプランコンテストというのが開催されています。近隣では岐阜県の多治見市において、たじみビジネスプランコンテストというのが毎年開催をされているということです。このコンテストで2023年にまちなかグランプリを受賞された方が、昨年10月におやつ屋さんを開店したとテレビで放送していたんですが、午前中で売り切れてしまうほどの人気店となっているということでした。ただ、それ、人気店なんですが、営業日は土曜日と日曜日だけということで本当に週末の起業なんですね。このような新しい形の起業をどう後押ししていくかというのが今の地域づくりには求められているのではないでしょうか。お隣の瀬戸市では、瀬戸くらし研究所さんがチャレンジキッチンというのをつくって、週1回お店を経営してみようというような取組もなされたりしています。
冒頭にて、本市はベッドタウンとしての特性を非常に強く持っているとお伝えしました。この特性を強みとして捉えて、あえて週末、土日のみをターゲットにした週末ビジネスプランコンテストをやってみるとかですね。これまでの常識にとらわれない新しい考え方で産業振興を進めていただけたらなと思います。
もう一つ、産業振興の方向性で私見をお伝えさせていただきますが、本市はその立地からいって都市型の商業施設ってあまりなじまないのではないのかなとも思います。名鉄瀬戸線に乗っちゃえば30分かからずに名古屋市の中心部、栄までばっと行けちゃうわけです。道路環境のよさからも、近隣市にいっぱい大型店舗はあるんですけれども、これも本当に自家用車で数十分、10分、20分走れば行けちゃうので、その点からいっても、本市では野外とか公園とか、そういう自然を生かしたところでどうお金を使ってもらうかというようなところもしっかり考える必要があるんじゃないかなということを踏まえまして、質問事項2のほうに移らせていただきます。
尾張旭市議会議員 かつまた修二公式ページをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。